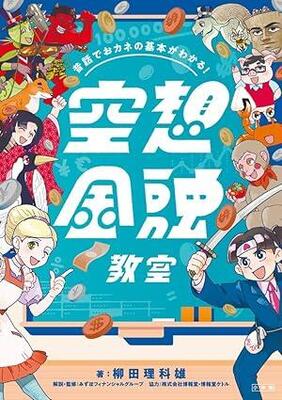
昔話を読んでいた子どものころ、あれこれと疑問を抱いたことはありませんか。「『さるかに合戦』のカニは、なぜおにぎりと柿のタネを交換してしまったの?」、「もっとみんなが幸せになれる未来はなかったのかな」と。でも当時は、そんな疑問を飲み込んで、物語の結末だけを楽しんでいた人も多いでしょう。
登場人物たちの選択は、本当に正しかったのか。今の自分ならどう判断するだろうか。たとえば、『さるかに合戦』のカニが、おカネや時間の価値を理解していたなら、経済的な視点からリスクを判断できたかもしれません。
そんな"昔話を経済の目で読み解く"という、ユニークで示唆に富んだ視点を提示してくれるのが、今回紹介する書籍『昔話でおカネの基本がわかる! 空想金融教室』(著:柳田理科雄)です。著者の柳田氏は、『空想科学読本』シリーズで知られる作家で、アニメや昔話の展開を科学的に検証するユニークな作風で支持を集めてきました。
本書では、みずほフィナンシャルグループ監修のもと、昔話に金融教育の要素を加えて、おカネの基本をわかりやすく解説しています。
たとえば、冒頭で触れた『さるかに合戦』の章では、サルとカニによる「おにぎり」と「柿のタネ」の交換に注目。そのやり取りを金融の視点から読み解きます。
「どれほどの実がなり、それによる収益はどれくらいか? それはリスクやコストに見合うものなのか? 物々交換とはいえ、取引である以上、そういうことを考えて行うべきなんですね」(本書より)
カニにとっておにぎりは"今すぐ食べられる"確実な価値。一方、柿のタネは"将来の果実"という可能性を持つ資産です。この交換は、一見単純な物々交換のように見えますが、金融的に見れば「将来価値に基づいた選択」という、投資や資産運用に通じる考え方の一端を含んでいます。
では、交換に応じたカニが悪かったのかというと、そうでもありません。
「サルにも問題があります。説明責任を果たしていません(中略)取引において、確実性の低いものを提供する場合は、相手にそのリスクを説明する必要があります」(本書より)
サルが発芽の失敗や育成コストなどのリスクについて説明しなかった点を問題視し、取引における「説明責任」の重要性をわかりやすく解説。サルからこうした説明があれば、双方にとって納得のいく結果になったかもしれませんね。
本書ではアナザーストーリーとして、カニがサルに対してリスク説明を求めて条件交渉する場面や、事業化して株式会社を設立し、臼たちに出資を募ったり事業を拡大したりする展開が描かれます。昔話の"もしも"を楽しみながら、金融やビジネスの基本を学べるのが、本書の最大の魅力です。
他にも、「『舌切りすずめ』で考える[金融トラブル]」、「『シンデレラ』で考える[生命保険の役割]」、「『かさじぞう』で考える[老後の資産]」、「『アリとキリギリス』で考える[おカネと働き方]」など、昔話を通じてさまざまなトピックを学ぶことができます。
金融教育と昔話という異色の組み合わせを、親しみやすく、かつ理論的にまとめた本書は、おカネに関する思考力や判断力を育むうえで、非常に有意義な一冊です。学生にとっては将来への備えを考えるきっかけに、社会人にとっては金融を見つめ直すヒントになるでしょう。金融や経済の基礎を楽しく学びたい人に、自信をもっておすすめできる内容です。気になる人は、ぜひ本書の特設サイトも覗いてみてください。
[文・春夏冬つかさ]

































