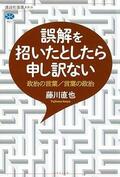例えば、自転車をこぐ時、手足の筋肉をどう使うか、体のどの部分でバランスを取るかとか考えないですよね。意識しすぎると、スムーズな動きができなくなってしまう場合もあります。でも、そんな人でも、一度理屈を知れば、新たに見えてくる景色がある。だから、結局どちらのタイプの方にも、音声学は助けになると証言してくれています。
発音や発声について、ほかにも知っておいていただきたいことがあります。例えば、女性の中には風邪をひいているわけでもないのに、声がかすれる、出にくいと感じるタイミングがある方もいます。風邪ではないのにそう感じることがあったら、もしかしたら身体のリズムと関係があるかもしれません。排卵周期と関係することも知られていて、実際に知っておくと安心できることもあります。このように、音声学は、身体の仕組みを知って、自分の声と仲良くなるきっかけにもなります。
──川原さんはNHKのアナウンサー向けの勉強会にも講師として参加されていますが、「声」や「言葉」のプロの人たちが音声学に興味を持ってくれているのは、なぜなのでしょうか。
歌手でもアナウンサーでも声優でも、上手に声は出ているけど、その時に肺や舌などの器官がどう動いているまでは理解していない人が多いです。うまくいっている時はいいけど、スランプが来た時に原因がわからなくなる可能性がある。一度落ちた調子を立て直すには、「はしご」のような役割が必要で、音声学は、その役割を担えるのではないでしょうか。もちろん、音声学は、すべての問題を解決できる魔法のツールではありません。しかし、発音の仕組みを理解することで、いざというときの対応ができるのではと最近は感じています。
──プロではない一般の人にも、そういった知識は役に立つのでしょうか。
最近は、「歌が上手になりたい」という目的だけでなく「滑舌をよくしたい」「演劇や朗読に活かしたい」「自分の思いをよりはっきり表現したい」などさまざまな理由でボイストレーニングに通う方が多いそうです。自分の声に少しでも興味があれば、音声学の知識はとても役立つと思います。
専門的な話になりますが、口の中の天井部分の後ろ側の柔らかい部分を「軟口蓋(なんこうがい)」といいます。よろしければ自分の舌先で確認してみてください。
たとえば、ボイストレーニングの発音練習の時、一般的に「軟口蓋を上げて歌いなさい」と言われることが多いのですが、日本語の「な行」や「ま行」は軟口蓋を下げないと出せません。けれども、むやみやたらと「軟口蓋を上げなさい」と指導するコーチもいると聞きます。音声学の理解にもとづいたトレーニングができるコーチはまだ少数派で、本書を通じてそういった思い込みや呪縛を解くことができたらと思っています。