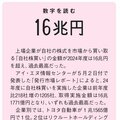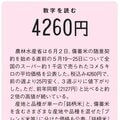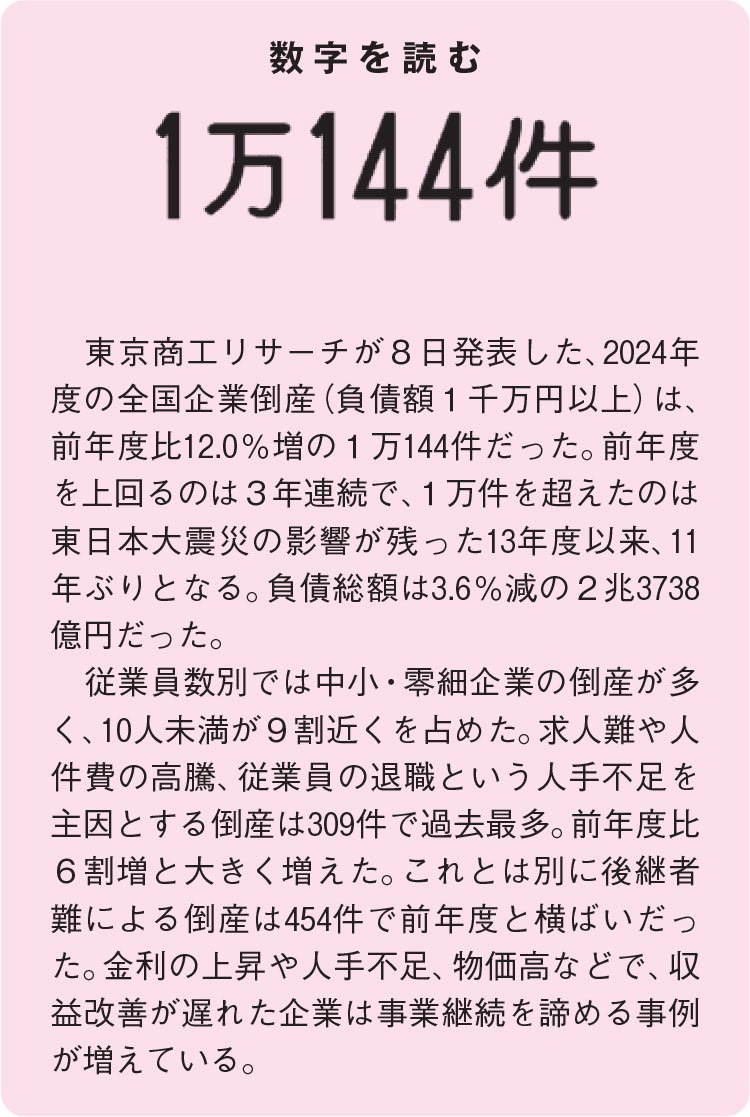
物価高や為替、金利など、刻々と変わる私たちの経済環境。この連載では、お金に縛られすぎず、日々の暮らしの“味方”になれるような、経済の新たな“見方”を示します。 AERA 2025年4月28日号より。
* * *
霜降り肉の脂が胃にもたれる。40歳を過ぎた頃から、赤身肉ばかり好んで食べるようになった。振り返れば学生時代も霜降り肉をほとんど食べなかったが、それはお金に余裕がなかったからだ。当時はお金の制約によって食べられず、今は健康の制約によって食べられない。同じ「食べられない」でも、理由は大きく異なっている。
私たちが日常生活や経済活動を営むうえでは、常に何かしらの制約が存在する。経済活動に必要な要素として、ヒト・モノ・カネの三つがよく挙げられる。日本が戦後復興を果たして以降、長い間「ヒト」と「モノ」は比較的潤沢だった。高度成長期やバブル期などの好況時や、災害時などには、一時的にヒトやモノが足りなくなるときもあったが、基本的に「お金さえあればなんとかなる」という状況だった。
経済を考える上でも、「いかに資金を調達するか」「どのようにお金を循環させるか」が主な議論になるように、大事なのは「カネ」だった。
ところが最近、状況が明らかに変化している。東京商工リサーチによると、2024年度の全国の企業倒産件数は1万件を超え、11年ぶりの高水準となったという。特に中小・零細企業の倒産が多い。興味深いのはその内訳で、「求人難」や「人件費の高騰」といった人手不足による倒産が前年度比で6割以上も増加し、過去最多を記録している。今や企業経営の最大の制約は「カネ」ではなく「ヒト」になってしまったのだ。