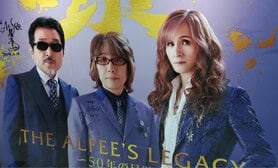現在、TBS系で放映されている『天皇の料理番』はこれが3度目のドラマ化で、番組のスタートにあわせて杉森久英の原作も復刊した。伝記小説の名手がモデルとしたのが、正式には宮内庁(戦前は省)厨司長を務めた秋山徳蔵。本文では秋沢篤蔵となっているが、この人物がいかなる気性の持ち主だったか、杉森はそこから書き起こす。
〈小さいときから、強情な子だった。
何かほしい物があると、手にいれるまであきらめない。あばれる。わめく〉
最後まで読んでふり返ると、篤蔵はこの幼年期の気性のまま生きたような気がする。小僧のスタイルがかっこいいと10歳で禅寺の小坊主になったが、やんちゃが過ぎて破門。その後、大阪で米の相場師になろうと家出して連れもどされ、仕出し料理屋へ養子に出される。そして、注文の品をおさめに行った陸軍の連隊でカツレツを食べさせてもらうと料理の虜となり、数え17歳で妻にも告げず東京へ家出。大学で法律を学ぶ兄の力も借り、鹿鳴館の後にできた華族会館に就職。下働きから料理人をめざした。
福井県武生の裕福な家の次男に生まれたという条件もあっただろうが、いざ目的が定まってみると、篤蔵は他の何倍も努力した。たとえば、料理用語であるフランス語を学ぶために12時間以上も働いた後に先生宅に通った。精養軒に転職すると、当時は唯一のフランス帰りのシェフだった西尾益吉料理長のノートを盗んで献立を学んだ。これなどは篤蔵の過剰な性分がやらせた蛮勇だが、21歳のとき、ついにフランスへ渡って本場の料理を体得。25歳で帰国し、厨司長となってから50年以上、大正天皇と昭和天皇に仕えた。
杉森は、「三つ子の魂百まで」を地でいくような篤蔵の生涯を淡々と描いている。激しい探求の人生だが、そこから浮かんでくるのは、惜しみなく生きた人物の堂々たる清々しさだった。
※週刊朝日 2015年5月29日号