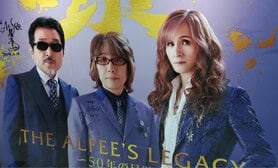今年のぼくの読書テーマは『平家物語』で、元旦からずっと読んでいる。『平家物語』には二つの大きな要素がある。一つはよく知られた諸行無常だ。しかしそれと矛盾するようだが、因果応報という要素もある。平家が滅びるには、それだけの原因があったのだ。
諸行無常だけだと、読者や聴衆は不安で楽しめない。因果応報ですっきりする。もしかして、エンターテインメントというのは、すべて諸行無常と因果応報のブレンドではないか……。
ってなことを伊坂幸太郎の新作『首折り男のための協奏曲』を読みながら考えた。もしも伊坂の作品を読んだことがない人がいるなら、本書は最適の伊坂入門となるだろう。
本書は七つの作品からなる短編集である。発表時期も、発表媒体も、作品の長さもそれぞれ異なる。もともと連作となることを意図して書かれたものでもない。しかし、一冊にまとめるために手を加えられ、並べられると、短編集というよりも変わった趣向の長編のように見えてくる。
冒頭の、そして七つのなかで最も早く発表された作品である「首折り男の周辺」には、伊坂的要素がたっぷり詰まっている。連続殺人犯であるらしい首折り男と、彼に瓜二つの気弱な男。クラスでいじめに遭い、不良たちに金銭を要求される少年。重い題材なのに、文体は軽やかで、ときどきユーモラスで、だからこそ読者はいじめられる少年に感情移入してしまう。悲劇と喜劇が同居すると喜劇になってしまい、そして読者の期待通り(でも読者の予想とは少し違う)ハッピーエンドとなる。
最後に収められた「合コンの話」は、若い男性会社員が合コンに行くだけの、これ以上はないぐらいくだらない題材を、徐々に肉付けして短編に仕上げていく小説である。ほんとうに伊坂幸太郎がこんなふうにして小説を書いているとは思わないけれども、まるでマジックでも見ている気分だ。
※週刊朝日 2014年3月7日号