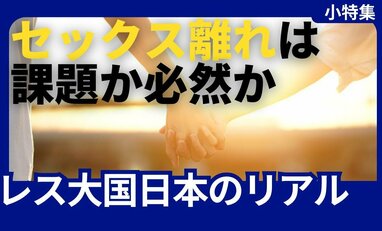――カメラは、いつごろから好きだったんですか。
小学生の高学年くらいからですね。遠足に親父からお下がりでもらったミノルタのオートコードを首からぶら下げていったくらいです。それから学校の行き帰りにわざわざ自由が丘駅で降りて、「一誠堂」というカメラ店のショーウインドーを毎日、眺めていました。棚に並んでいた順番まで覚えています。一番上が王様のニコン、次がキヤノン7、そしてペンタックスSPでした。最初に買ってもらったカメラはフジペットだったんですが、やっぱり一眼レフはミラーが上下するときの音が特徴的じゃないですか、それがいいんですよ。しかもシャッターを切るとミラーが瞬きするのが見える。こいつがなんとも……(笑)。とくにペンタックスはデザインに憧れていました。ぼくが子どものころ「原子力潜水艦シービュー号」というテレビドラマがあって、それが唯一、旭光学提供の番組だったんです。ドラマよりもCMが見たかった。「ペンタックス、ペンタックス。望遠だよ、望遠だよ」というセリフは今でもよく覚えている。
だから中学1年生のときにペンタックスSVを買って帰ったときは、「あり得ないもの買ってしまった」という興奮で、その夜は眠れなかったですね。でも、そのSVは親父に取り上げられてしまったんですよ。
――それはどうして?
じつは……SVを買うために祖父のお金をくすねていたのがバレてしまって(笑)。祖父は家作を持っていて、家賃が当時は現金書留で送られてきたんです。そのお金を抜き取って、封筒はハサミで切り刻んでトイレに流して、自分では「完全犯罪だ」と思っていたんですけれど、寝言でうっかり口を滑らせてしまったみたいです(笑)。取り上げられたSVは高校生のときに返してもらえました。
そのあと叔父の遺品でライカをバルナック型からM型まで、10台くらい譲り受けました。叔父はゴルフ場を経営していて、そのコースの写真などをライカで撮っていたのをよく覚えています。とくにこのライカⅢは叔父が初めて買ったライカなので、ぼくも思い入れが深いですね。
いま持っているカメラは30台くらい。コレクターじゃないのでレアモデルとかじゃなく、むかし自分が憧れていたカメラばかりです。カメラにオーラがあったのが1970年代までだと思うんですよ。ポジションも全然違った。70年代からこっちは単なる「写真を撮る道具」。それ以前はカメラは車と同じように別の意味を持っていて、ステータスとか、カメラそのものが偉そうな雰囲気がありましたよ。
――それが最近になって、リコーGRデジタルを買われたのはなぜでしょうか?
こいつは、ぼくの中で初めてライカに勝ったカメラなんです。最初はライカM8が気になっていました。でも、友人がGRデジタルで撮った猫の写真を見て感動したんです。まるでアナログカメラのような奥行き感と、デジタルならではの硬さ、くっきり感の両方を持っている。ライカのよさってコンパクトなボディーでしょ。するとあれだけの機能をよりコンパクトなボディーに収めるというのは、大きなM8よりGRデジタルのほうがむしろライカ的な発想に近いんじゃないかと思いました。
ぼくが音楽の世界でアナログからデジタルに移行したのは、81年のアルバム「昨晩お会いしましょう」からなんです。そのときはアナログで作っていた音と全く違うイメージで愕然としましたよ。まるで大きなお皿に料理がチョコッと載っているスカスカな感じで、この隙間をどうやって埋めようかと。それ以来、ぼくの中では「アナログとデジタルは別もの」という感覚ができていたんです。カメラについても同じ。でもそんな諦めもGRデジタルと出合って変わりました。
――写真はどんなものを撮るのですか?
モーターショーの取材では、GRデジタルにワイドコンバージョンレンズを付けて運転席からインテリアまでの車内を撮ります。でも音楽の仕事ではなかなか撮らないですね。コンサートの準備をしているときは自分が制作のど真ん中にいるわけですから、メーキングの写真なんか撮っている余裕はないですよ。やっぱり写真は、自分がどこか傍観者的な立場のときですね。
ライカの叔父もそうだったんですけど、ぼくは人にレンズを向けるのが苦手なんです。人を撮るのって、撮られる側と関係性を作って、その人の領域に入っていかなくちゃけない。そのエネルギーたるや大変なものでしょう。そんなの簡単に撮れないって。だからぼくにとってカメラとはもっぱら仕事の気分転換にいじるためのもので、撮るのは二の次。
かみさん(松任谷由実)ですか? たまーに撮るときもありますよ、カメラがいじりたいときに(笑)。カメラは家の棚に並んでいるんだけれど、「趣味がいっぱいあっていいわね」と言ってくれてます。(笑)
※このインタビューは「アサヒカメラ 2008年2月号」に掲載されたものです