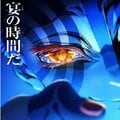■「女を喰う」「女を喰わない」
猗窩座が女を喰わないことは、彼が鬼になった経緯と関係している。童磨は「猗窩座は女を喰わない」と言ったが、「喰えなかった」というのが正しいのではないか。しかし、鬼として生き、強さを求める猗窩座が、人を喰うことにためらいを見せることは、本来であれば許されない。
「だけど猗窩座殿って女を喰わない上に殺さないんだよ!それを結局あの方も許してたし ずるいよねぇ 猗窩座殿は生かされてた 特別扱いだよ」(童磨/18巻・第157話「舞い戻る魂」)
鬼は人間を喰わねば生きていくことができない。鬼でありながら、「鬼らしさ」の一部を受け入れようとしない猗窩座を童磨は不満に思っていたのだろう。童磨は堕姫・妓夫太郎を鬼になるように誘うことに成功し、彼らは敗北はしたものの、上弦の鬼にまで成長している。また、彼が”栄養価の高い”女を喰うことは、たくさん人間を喰うことで強くなれと命じる無惨の志向と合致しているといえる。童磨はみずから人間らしい感情がないと言うが、それでも「他の誰かが望む自分」でいようとする、意外な一面がここで見えかくれする。
それに対して、猗窩座が鬼になるように勧めるのは、自分が気に入った人間だけだった。“殺戮”も“食”も自分の思いが先行している。無惨が求めるままに「鬼らしく」生きようとした童磨と、「鬼としての性(さが)」に嫌悪を示す猗窩座は、これほどまでに正反対だ。
■2人が思い描いた「鬼」としての生き方
上弦会議でぶつかった猗窩座と童磨は、再び無限城にあらわれるその時まで、しばらく登場する場面はない。刀鍛冶の里編以降に制作が期待されている「無限城編」では、童磨が「鬼としての役割」を果たそうとする様子と、それが何に由来するものなのかが描かれる。また、猗窩座は「鬼としての生」の中にありながら、人間時代から手放せない、物狂おしい後悔を語る。
この2人の鬼のエピソードで明らかになるのは、彼らの顔に浮かぶ「優しさ」と「狂気」だ。「鬼らしい」のはどちらか。彼らは「人間らしさ」とどのように向き合うのか。さらに深まっていく、上弦の鬼たちの物語も、今後の大きな見どころとなる。

◎植朗子(うえ・あきこ)
1977年生まれ。現在、神戸大学国際文化学研究推進センター研究員。専門は伝承文学、神話学、比較民俗学。著書に『「ドイツ伝説集」のコスモロジー ―配列・エレメント・モティーフ―』、共著に『「神話」を近現代に問う』、『はじまりが見える世界の神話』がある。AERAdot.の連載をまとめた「鬼滅夜話」(扶桑社)が好評発売中。