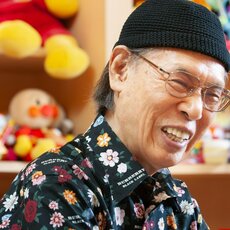「詰め込み」「偏差値」というイメージが強い中学受験。「受験のための勉強は子どもの将来に役に立つの?」「難易度より、子どもを伸ばしてくれる学校を選びたい」といった悩みを抱えている親御さんも増えています。思い切って「偏差値」というものさしから一度離れて、中学受験を考えてみては――。こう提案するのは、探究学習の第一人者である矢萩邦彦さんと、「きょうこ先生」としておなじみのプロ家庭教師・安浪京子さん。連載「偏差値にとらわれない中学受験相談室」、今回は、美術科のある中高一貫校を目指している小5女子のお母さんからのご相談です。
【マンガ】中学受験で合格したのに…「やっぱり地元の公立中に行く」 息子の告白に両親が出した“答え”とは?(全35ページ)「マイナス発言」は自信がないから、だけではない
矢萩:まず「マイナス発言」をする理由ですが、これは単に自信がないから、というだけではありません。実は、ある程度のシミュレーション能力を持っている子どもによく見られるんです。完璧主義的な傾向があって、ゴールを具体的に思い描ける。その一方で「自分にはそこまでできない」と感じてしまう。その結果、「だったら最初からやりたくない」と言ってしまうんですね。つまり想像力も構築力もあるのに、理想と現実とのギャップを埋められる自信がなく、やる前から「嫌だ」と言ってしまう。こうした子は今、とても多いです。
安浪:親から見ると「なんでそんなにマイナス発言ばかりなの?」と思うかもしれませんが、本人は未来の姿をリアルに想像できる分、そのギャップに敏感なのかもしれないですね。「こうなりたい」という理想が明確だからこそ、「今の自分には無理かもしれない」と怖くなってしまう。
矢萩:そうなんです。むしろ「ビジョンを立てられる」というのは才能なんですよ。大人の場合は必ずしもそれではないですが、子どもの場合、マイナス発言をするということは、やりたいことと現状のギャップを比較してシミュレーションできる能力があるということもあります。その能力はぜひ認めてあげてほしい。そして、お金をかけなくても工夫次第でできることはたくさんあります。たとえば絵を描くのが苦手でも、頭の中に完成イメージがある。だったら言葉で説明してAIに描かせる、といった新しい方法だってある。どんな方法があるかを家族で一緒に探すことも大切ですね。
次のページへ美術を学ぶ方法は学校だけではない