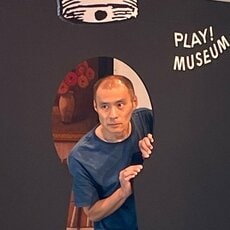今年の夏休みは、「お手伝い」を通して子どもの「生活力」を上げましょう。生活力は、日常で駆使するさまざまな「スキル」の集まりといっても過言ではありません。「お手伝い」は、まさにスキルの練習。継続することで成長にも大きく影響します。育児のカウンセリングを行う公認心理師の佐藤めぐみさんにお手伝いでスキルを上げるコツを聞きました。子育て情報誌「AERA with Kids2025年夏号」(朝日新聞出版)からお届けします。
【図】学力が高い子の家庭に見られる8つの特徴(全8枚)勉強も大切ですが、生きる 基本となる力も重要です
生活力と聞いてまず思い浮かべるのが「お手伝い」。「家事は『できる』ほうが絶対にトクです。なぜなら、自分で考え、自分で動くことができるからです」と話すのは、行動改善プログラムを用いて育児のカウンセリングを行う、公認心理師の佐藤めぐみさんです。
「お手伝いでは、技術の練習、習得がおこなえます。このスキルは、生活力として将来、どこかの場面で必ず使う“材料”や“部品”のようなもの。勉強ももちろん大切ですが、お手伝いで身につけた部品たちが役に立つことも、この先多々あるでしょう」(佐藤さん)
思春期に入ったら、親の助言に耳を貸さないことも
お手伝いは、子どもの“心”にも効果をもたらします。
「中学生になると、自立に向けて親と距離を置く子どもが多いですが、小学生時代にお手伝いでスキルを培っておけば、それを自分の自立行動に応用できます」
ひとつの家庭に数年にわたり並走し、子どもの成長を見守るケースも多い佐藤さん。
「小学校高学年~中1くらいで『思春期』に入ります。親との距離感が変わり、自立したい気持ちが大きくなる時期。しかし、そのときに自分に生活力がないと“親がいないとなにもできない”未熟な自分を突きつけられて、『なぜ自分はこうなんだろう』と、より反抗が強くなるケースもあるのです」
思春期本番、身のまわりのことがある程度自分でできるということは、とても大切なのです。
「この時期になると、親の言うことには耳を貸さなくなります。となると、生活力の基礎づくりは、小学生の今がベストでしょう」
この夏休み、さっそくお手伝いをスタートしませんか?
次のページへお手伝いで積み上げられる「部品」とは?