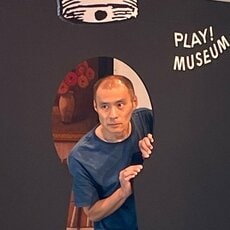子どもが勉強しやすい環境づくり
まず、「親子で勉強タイムの設定」です。
「子どもは宿題しなさい」と言って自主的にできるかといったら、子どもは今を楽しむプロフェッショナルだから、なかなか難しいんです。
なので「お母さんもここで明日の朝ごはんの準備するから一緒にやろう」と言って、ダイニングで宿題をする子どものそばで家事をするのです。
家事でなくてもよくて、仕事をしてもいいのです。横にいてあげることが、子どもにとってはとても励みになります。
横に座って勉強をみてあげるということではありませんよ。親は親のしたいことをしていればいいし、子どもに質問された時には答えればいいですが、監視するのでもありません。
「勉強タイムだよ」と言って、「一緒にやる」のです。「メロディ時計の導入」も効果があります。子どもが時間管理できるようになります。
「メロディ時計」とは、鳩時計のように、3時とか8時とか時間ぴったりにメロディーが鳴るような時計です。
このメロディー時計を我が家では導入していて、ティラリリーンと鳴ると「あ、今、何時だ」ってみんな、時計を見るんです。メロディが鳴ったら私も言いやすいので、「あ、9時だ」と時間を口にします。
ここで、「9時だから〜しなさい」ではなくて「9時だ」というふうに時間を言うだけでいいんです。そうすると子どもも時間を意識するのが習慣になって、時間管理も身につけやすくなるのです。
「宿題&親vs子ども」ではなく、「宿題vs親&子ども」
また、「甘いものから勉強タイムに突入」という仕掛けもやりました。
宿題をする時間になったら「ゼリー食べる人〜?」などといって子どもたちをおびきよせるのです。
冷凍のフルーツマンゴーやアイスを「冷たい冷たい」と言いながら食べたりするので、宿題には果物やアイスの汁がついたりしましたが、全然それでOKです。
宿題を神々しくしないためにも、「甘いもの」を導入するのです。
「宿題やりなさいよ」と怒るのではなくて、「宿題デザートはゼリーだよ」などと言うのです。食後にデザートを食べるなら、どうせなら私は、「食後」に出さないで「宿題タイム」に出していました。
次のページへ宿題は一緒にやっつける