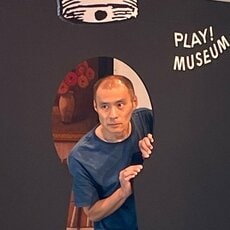たとえば、今夜の、このイベントのような活動・仕事があったとしても、子どもには全然ノーケアで、親は全力投球できます。
もちろん、小学生、中学生ぐらいまではいろいろと大変なこともありますが、そのときに「子どもを自走化する」に特化して、そこにエネルギーを集中させるのです。
そういうふうにすると、将来が楽になるメソッドが「戦略的ほったらかし教育」なのです。
宿題バトルをしていませんか?
戦略的ほったらかし教育の本質になりますが、「ほったらかし」と「戦略的ほったらかし」はどう違うと思いますか。
「ほったらかし」は「無関心」だったり「放置」ですね。
「戦略的ほったらかし」は、「仕組み」と「信頼」で支えて「自立」を促していきます。
「子育ての環境整備」を行うところが「戦略的」なのです。
書籍には具体的な事例もたくさん載っていますが、そのなかからここで少しご紹介できたらと思います。ぜひぜひこの夏休みに挑戦してみてください。
皆さん、お子さんと宿題バトルしたこと、ありませんか。
放っておいたらいつまでも子どもは宿題をやらない。でも、自分も忙しくて面倒見きれない。もう自分でやってほしい。
計画を立てても、その通りやらない。つい命令口調になってしまい、子どもとバトル、そしてその後自己嫌悪……。もう注意するのも疲れたーー。
夏休みの最後に親の負担が爆増ということがあるかと思います。でも、子どもが「やらない」のではなく「やれない」状態を親がどうサポートするか、というのが鍵です。
まだまだ子ども自身は、習慣にする力がついていませんし、先を見通す力も、もうほとんどないに等しいです。
なぜなら子どもって「今」が楽しい生き物なんです。子どもは今を楽しんでいて、先の心配をしているのは親です。
テレビを見ていたとしても親は、「何時に寝かせないと」とか「洗い物も終わっていないな」とか「明日の会議の資料作りがあと少しだけ残っているな」などと心配します。
一方の子どもは、「今」に集中して楽しんでいる。子どもは、本当に今を楽しむプロフェッショナルなんです。なので、「やれない状態」が当たり前。そこを、どうサポートしていくかというところが鍵になります。
次のページへ横にいてあげることが大切