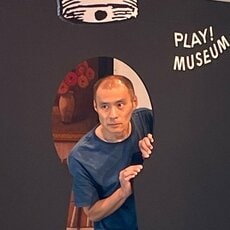料理のレシピは、数字がたくさん出てきます。「大さじ1って何ccだっけ? こっちは45mLって書いてあるけれどこれって大さじいくつ?」など、体積の単位は算数に必ず出てきますし、また野菜の産地は社会に役立ちますし、材料の変化は理科の実験のようです。
意外かもしれませんが、料理のレシピを理解するには、読解力が必要なのです。レシピは非常に無駄のない文章で書かれていますから、途中出てくる料理用語を知らなければお手上げですし、順序よく作らないと美味しい料理ができません。レシピは、読みながら料理を進めていくと炒めすぎたり、焼きすぎたりします。ですから、まずはレシピを読み込んで、頭の中で映像化して手順を確認する必要があります。手順をマスターして料理を始め、頭の中の映像に従って時々はレシピの文で確認しながら進めると、写真通りの料理が出来上がるのです。
これは、国語の物語文などを読んで主人公の様子を映像化し、質問に答えていく作業と非常に似ているところがあり、料理をしていると自然と映像化を伴う読解力がつきます。わが家の子どもたちはみんなレシピを読むのが大好きでした。
料理は家の中で手軽にできますし、何より出来上がったものを家族みんなで食べたり、ワイワイ感想を言い合ったりと、楽しいことがたくさんあるのでおすすめです。
わが家の夏休みの楽しみの定番といえば、かき氷、花火、プールでした。でも6年生になると分単位でスケジュールを組んで勉強するようになりますから、受験生にお楽しみはなし。さらに受験生がいる時は、他のきょうだい3人もその年はお楽しみはなし、というルールにしていました。
プールはともかく、かき氷や庭先でやる花火ぐらいいいじゃない、と思うかもしれませんが、かき氷を4人分作るとなるとワイワイガヤガヤ結構時間がかかります。花火は受験生が塾に行っている間にすることもできますが、受験生が夜帰ってくるとどうしても残りの3人の顔に花火をやったワクワク感が出てしまうんです。
次のページへ兄弟4人は一蓮托生