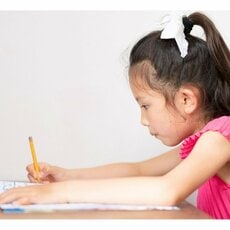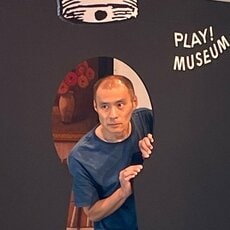子どもたちが寝た後、明日1日のスケジュールを書き出していくのです。時間とやることを書いているうちに、明日の自分の動きがシミュレーションできます。次の日の朝に、「さあ、今日は何があるんだっけ」などと思うのでは1日をスムーズに過ごせません。空いたスペースに自分の気持ちや子どものことで気づいたこともメモするようになり、次第に日記がわりにもなっていきました。
子どもたちが小学生のうちは全部私がスケジュールを作っていました。小学生はまだ自分で予定を組むのは難しいと思います。
食事の時間や寝る時間など、大人の都合で変わってしまうこともありますし、第一、子どもは全体を見通すことが苦手です。そこは、やはり人生経験豊かな大人が作るべきでしょう。作る時に、子どもの意見を取り入れながら仕上げると、子どもも自分のものだと思いますから、しっかりそのスケジュールを守ろうという気持ちになります。
小学校1年から6年の間の子どもは日々成長していますから、4月に作ったスケジュールを1年間使えるということはありません。子どもの考え方も成長して変わってくるので、ちょこちょこ微調整が必要なのです。
子どもたちが中学受験の塾に行くようになると、私のノートの1ページでは書ききれなくなったので、子ども1人に大学ノート1冊を使い、表紙に子どもの名前を書いて、それぞれにやることを毎日書いていた時もありました。子どもたちは、そのノートを見ながらその日にすることを確認して、済んだら横線で消していました。
5年生頃になって宿題が多くなったり、テストに向けた準備が必要になると、1週間単位のスケジュール表もよく作りました。
A4の紙を横にして7つの枠を作って日付と曜日を書き、その下にやることを書き出すのです。塾の宿題をどう割り振ってやるかを考えるためには、1週間単位のスケジュール表を作って進めていくのがベストだと思います。
一度作ったものでずっとやろうとすると、歪みができて子どものやる気を削ぐことにもなりますから要注意です。子どもは、日曜日から土曜日の1週間単位で生活していますから、まずは1週間の予定を作る。その通りにやってみて、改善するところは子どもと相談して調整し直す。調整したものを1週間やってみて、またちょっと微調整。それでほぼ、完成ですから、その予定で1か月は頑張ってみましょう。
次のページへ親がスケジュールを立てると、子どもの自立が阻まれる?