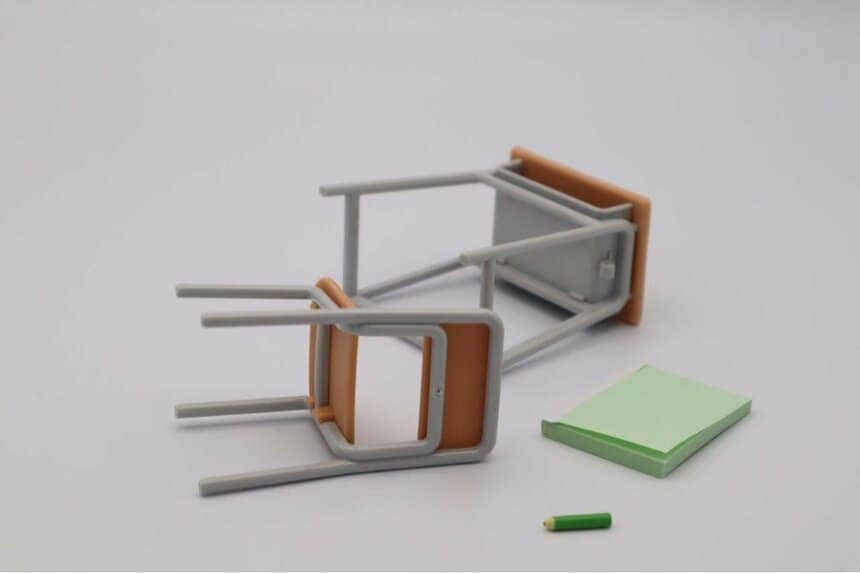公立中学校への“誤解”
早見:第1志望に受かったからといって幸せなわけじゃない。落ちたから不幸せということでもない。実際にそれは、生徒たちにきちんと伝わっている実感はありますか?
東田:第1志望でない高校に行っても、その学校で“別の自分が見つかりそう”という気持ちが持てるかどうかで変わります。どんな学校にも良さはあり、気の合う友人や先生は絶対にいます。
でもなかには「大学受験でリベンジする」という生徒もいます。すると、高校の3年間が過去の屈辱を晴らす時間となってしまう。そして残念なことに、大学受験でもまた失敗する生徒もいる。中学受験と高校受験に共通していえるのは、「第1志望に受からなきゃいけない」という刷り込みを取っ払う“大人の声かけ”です。
公立中学校の位置づけも大切です。あんな学校は学習意欲がない子が行くところだよという印象を親が持っていると、子どもに伝わります。事情により、地元の公立中学校に進むことになった場合、子どもは「なんでこんな学校に通っているんだ」と不登校になったり自信が持てなくなったりして逃げ道を失う。私はむしろ「公立中学校は選択肢でありだ」と伝えています。
早見:僕も中学受験を経験しています。私立中学校を受験すると決めて担任の先生に相談すると、嫌みを言われたことを今でも覚えています。
僕の担任の先生のスタンスもそう、公立中には進学しないと決めている今の子どもたちのスタンスもそう。全部“選民思想”に近くて、ポジショントークでしかありません。大切なのは進学先ではなく、どれだけ幸せな人生を送れるかという生き方です。

母親という“脚本家”、父親という“共演者”
――母親の立ち位置が『問題。』ではとても印象的に描かれている。
東田:『問題。』は、母親が仕掛けた物語だと分析しています。父と娘の関係を修復するために、母親があえて中学受験という舞台を用意したのだ、と。
早見:その通りです。娘に「選ばせている」つもりでも、実は母親が見えない脚本を書いている。それに父と娘が気づかぬうちに踊らされている。
次のページへ親の役割は何か