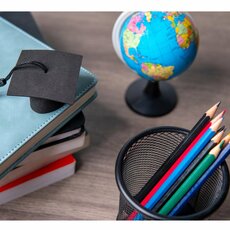現在ほど国や自治体からの補助金が多くなく、小学校の余った教室を転用した施設も少なかったので、エアコンの設置がとても間に合わない学童が全国あちこちにありました。エアコンがあっても、学童利用の保護者が引っ越すときに学童に寄付してくれた家庭用エアコンということが珍しくありませんでした。学童への補助金が徐々に充実したことで、夏場は涼しく過ごせる学童がかなり増えました。
市区町村における熱中症予防に関する情報の共有がだいぶ図られるようになって、学童における熱中症対策に役立っています。市区町村の教育委員会等が翌日の暑さ指数の予測や当日朝の最新の暑さ指数の予測について区域内の学校と情報を共有し、屋外での活動に注意を喚起することは以前から行われていましたが、その暑さ指数等の情報の共有に学童も対象として含める自治体が増えています。
学童を担当するのは教育委員会であったりそれ以外の福祉関係の部局であったりしますが、部や課を超えて熱中症の発生予防に必要な情報を市区町村内部で共有できる仕組みが整いつつあります。これも十数年程度前ではほとんど考えられなかったことです。
学童側は事前に得た情報を基に、あそびの時間や場所を調整します。「午前中なら外遊びできそうだ」となれば宿題の時間を午後に回したり、日陰で十分に休める場所であることを前提に「20分遊んで15分休憩する」などと取り決めたりして、休憩時間には必ず水分を取らせ、塩タブレットなどで塩分補給もするようにしているところがほとんどです。
そのほか、職員は子どもの様子を常に観察し、体調が悪そうな場合には声をかけて体温を測定したり涼しい場所で休ませたりなどの対応を講じます。たいていの学童では、夏が始まる前に職員は熱中症対策について事前に医療関係者からレクチャーを受けるなどして学んでいます。
暑いなかで困るのは「遊びの幅」
熱中症警戒アラートが出ると屋外での活動はできません。学童内で遊んで過ごすことになります。2020年代以降、毎年の猛暑で夏休みは外で思い切り遊ぶということができなくなりつつあります。
次のページへ熱中症対策には家庭の協力が不可欠