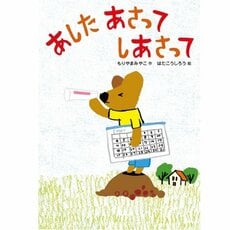入園や親子遠足、新しい習い事など、イベントが目白押しで子どもの写真や情報をSNSにアップする人も増える時期です。しかしなんでも調べられるこの時代。情報はどこまで出してOKなのでしょうか。SNS投稿する際の線引きとなる考え方や将来的なリスクについて、ITジャーナリストで成蹊大学客員教授の高橋暁子さんに聞きました。
【マンガ】子どもはスマホで何の動画を見ている?親が意外だった“勉強”への活用法(全10枚)価値観が分かれる親の「シェアレンティング」
「子どもが3歳になったので顔出し投稿をやめます」
こうした投稿がSNS上で目立っています。一方、子どもの顔や近所の写真をアップし続ける投稿もあり、価値観は二分しています。それが原因で人間関係に歪みを生むことも。
未就学児を育てる都内の30代男性は、SNS投稿への価値観の違いから仲の良かった友人への印象が変わったと打ち明けます。
男性はインスタグラム(以下、インスタ)のアカウントに鍵をかける慎重派。我が子の写真をSNSに投稿したのは一度限り。友人限定のアカウントで誕生を報告しました。一方、同時期に親になった知人女性は大のインスタ好き。双子を子育中で、生まれる前のエコー写真からマンスリー写真まで、子どもの写真を載せるだけのアカウントも作っています。両親の顔は出さないのに子どもの顔は投稿し、家が推測されやすい近所のカフェ情報も頻繁に投稿していることに男性はモヤモヤ……。
「カフェまで載せると行動範囲が分かるし、ましてや双子だから目立つ。ここまで子どものことを載せていいのかな?特定されないか心配……」
男性はインスタ投稿から友人に対し、不信感を抱くようになりました。
保護者が子どもの許可を得ずに子どもの写真や動画などをSNSやネットなどで公開するシェアレンティング。シェア+ペアレンティング(子育て)の造語です。親のリテラシー不足を問題視するのはITジャーナリストで成蹊大学客員教授の高橋暁子さんです。
「シェアレンティングは身近な問題で、実際に周囲でもかなりあります。対象となる子どもは一般的には未成年が対象ですが、ある程度大きくても子どもの同意を得ないで勝手に公開している場合はアウトだと思います。中には子どもたちの上半身裸の水遊びや入浴シーンをSNSにあげている人もいます」と高橋さんは語ります。
次のページへ掲載を控えるべき写真の線引きは?