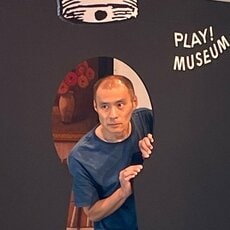できるだけ1日にたくさんの物を持って来ないでいいようにしたつもりでした。
「雨が降ったら、傘を持たないといけないから、無理しないでね」とも伝えていました。私は自分のことを“なんて優しい配慮ができる先生なんだ”と思っていました。
しかし、登校時、「先生、地獄や~!」「死にそう~!」と言いながら、荷物を持って教室に入ってくる子どもがいました。
体操服とお道具箱を両手に持って登校していたのです。絵の具セットを肩からかけ、習字セットを持って登校していたのです。
欲張って1度に持ってきた訳ではありません。前日に持ち物を忘れたから、翌日、前日分の荷物と当日分の持ち物を持って登校していたのです。朝からヘトヘトで教室に入ってくる子どもの姿を見て、忘れ物をするのが悪いとは到底思えませんでした。
普段だったら、「『死ぬ』『死にそう』なんて言葉、簡単に使ったらあかん!」と言って指導するのですが、子どもの苦しそうな表情を見ると言うことができませんでした。
私が立てた計画は、持ち物忘れをする子どものことを考慮した計画ではなかったのです。優しい配慮ができる先生なんかではなかったと気づきました。
重たい荷物を持った子どもたちの姿を見て、学級担任として重たい気持ちになりました。
どうすれば、子どもの荷物の負担感を減らせるのだろう
持ち物忘れの子どもが出ることを考えて、もう少し余裕をもって計画を立てればよかったのです。連日、新しい持ち物を持って来させないで、最低でも1日おきにすればよかったと反省しました。
具体的には、次のようにします。
こうすることで、例えばお道具箱を持ってくることを忘れても、次の日の持ち物が重なって苦しむことがなくなります。
次のページへ子どもに任せて気づけたことも