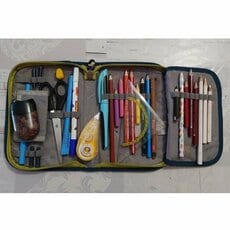首都圏を中心に相変わらず人気がある中学受験。競争の激しさが増す一方で、親も子も目の前の「受験勉強」に追われがちです。しかし、長い目で中学受験を見ると、中学受験にはアナログ的なトレーニングの場になる、と語るのは4人の子ども全員を東大理三に合格させた佐藤亮子さんと、数多くの受験生を志望校合格へと導いてきた中学受験専門カウンセラー・安浪京子さん。本記事では、2人の共著『中学受験の意義 私たちはこう考えた』から一部を編集し、“中学受験の意義”についてお届けします。
【マンガ】「偏差値の高い学校」への思いを捨てきれなかった母が、「路線変更」を決断して“わかった”こととは(全38枚)安浪:今GIGAスクール構想下で公立学校にデジタルが入ってきているじゃないですか。私の住んでいる自治体はいち早く学校のICT化に取り組んで、タブレットの配布も早かったんです。でも授業参観に行ったら、一部の子たちは後ろから丸見えなのがわかっていないのか、タブレットでゲームしていましたが。課題や宿題もタブレットに入っているドリルアプリから出て、漢字はタブレット上に指で書くんです。指が嫌だとペンツールで書くんですが、これがまた反応が悪い。普通、鉛筆で文字を書く時は小指側の手の側面を紙につけますよね。でもタブレットはそれに反応しちゃうから、手を浮かせて漢字を書かないとダメなんです。さらに採点はドリルアプリがする謎基準。だから、なんでこれがバツになるのかわからないっていうことも多々起こります。
佐藤:なんと!
安浪:あと、宿題も今までだったら1日あたり漢字ドリル1ページ、計算ドリル1ページとか細かく区切られていたのが、主体性を持たせるためだか何かわからないけれど、1週間分をバンとタブレットで出されて、自分のペースでやってね、というやり方になったり。よほど成熟度の高い子なら計画性を持ってやるだろうけれど、できない子は絶対やらないでしょう。
佐藤:そうなんですか。ちょっと悲惨ですね。
安浪:現場の先生たちもすごく憂いていました。このやり方では学力がつかないって。しかもそのタブレットも接続状態が悪いと悲惨です。やっている最中に画面が落ちちゃったりすると、また最初から。だから従来みたいに漢字ドリル1ページをアナログに取り組めば3分で終わるのに、タブレットだとその何倍もかかることがある。結局予想通りというか、漢字ドリルは半年後、紙に戻りましたね。
次のページへ中学受験をする新しい「意義」