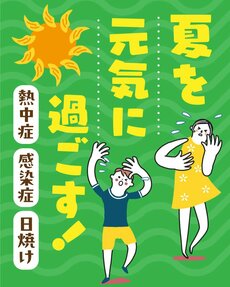佐藤:訳のわからない労力が発生するということですか。たかが小学校の漢字ぐらい、タブレットがなくてもね、さっさと書いて覚えるだけですよね。

中学受験の新しい意義とは?
安浪:だから私、ここ1、2年で中学受験をすることに新しい意義が出てきたと思っているんです。塾の勉強はまだアナログじゃないですか。板書を写して、ノートに書いて、というアナログの力が鍛えられる、貴重な場といえるのではないかと。
佐藤:なるほどね。私は大学受験までの18年間のうち、小学1年生から6年生までの6年間に学ぶ基礎学力って本当に大事だと思っていて。それこそ人生の土台です。基礎学力って相当アナログ的なトレーニングが必要なんですよ。人間ってそんなに簡単には賢くならないです。でも「大事だよね」と言っているだけだと子どもはしっかり学ばないから、その延長線上に中学受験を置くことで、真剣に学びますよね。中学受験にはそういう意義もありますね。
安浪:おっしゃる通り、基礎学力はアナログのトレーニングが本当に大事です。計算とかも受験がなければあれほどやらないですしね。それこそ鉛筆を持って手を動かすアナログの作業が必要で、タブレットではない。
佐藤:そう。それも小1から小6までの間に子どもはどんどん成長するので、その年齢に合ったトレーニングが必要です。そういったことが最近の学校教育ではないがしろにされているような気がします。
安浪:そうです。だから中学受験の再定義としては、アナログ的なトレーニングを積んで基礎学力を身につける機会である、ということ。そこには志望校の合格が関わってくるからより真剣にも取り組むわけで。
佐藤:そうそう。合格は後からついてくる感じかな。それも第1志望でなくていいんです。中学受験の勉強をしたことが大事なのですから。
安浪:ここ数年、中学受験が過熱して、教育虐待の話も多いじゃないですか。私自身も中学受験で親子関係が壊れていった家庭をたくさん見てきたので、そのような発信もしてきました。それらの影響もあってか、「そんなに厳しいなら中学受験はやめよう」と回避するご家庭も増えているようです。でも、佐藤さんとお話しする中で、学ぶ場を選ぶため、というだけに留まらない中学受験の意義を再確認した感じです。
次のページへ小学校の勉強ってなんてすごいんだろう