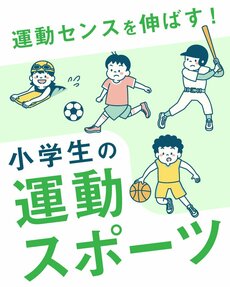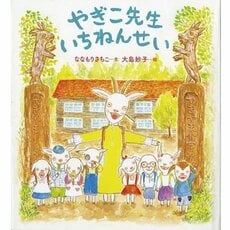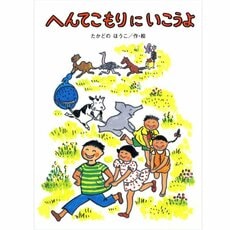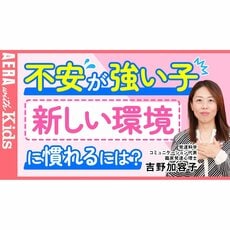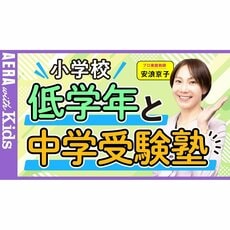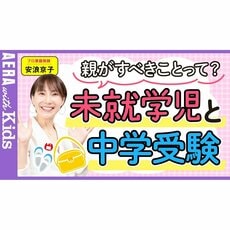早生まれのお子さんの学業、特に受験に関心を持たれている方も多いと思います。早生まれは中学受験において不利というデータがある一方で、高校受験・大学受験と成長するにつれて、遅生まれとの差は次第に消失していくといいます。難関国立大学や医学部の新入生のデータなどからくわしく見ていきましょう。脳医学者の瀧靖之さんの著書『本当はすごい早生まれ』から紹介します。
【ランキング】国公立大&全私立大医学部の「合格率」TOP30はこちら(全3ページ)大学受験で早生まれにもはや「不利」はない
多くの方の最終学歴となる大学のデータを見ていきましょう。
川口大司教授の「誕生日と学業成績・最終学歴」の数字によると、同じ年の最年長者(4月2日生まれ)と最年少者(4月1日生まれ)を比べた研究では、4年制大学卒業者の割合としては、最年少者の方が「男子で2%ポイント、女子で1%ポイント低い」という結果が出ています。全体における4年制大学卒業者の割合が、男子27%、女子9%であったことを考えると、無視できない結果です。
全体像を捉えたうえで、次のデータを見ていきましょう。
こちらは最難関とされる国立大学の数字です。ある年度のサークル構成員の新入生(男子30 人、女子41人)の割合を、「4月2日〜6月(遅生まれ・春)」を1とし、「7〜9月(遅生まれ・夏)」「10〜12月(遅生まれ・冬)」「1月〜4月1日(早生まれ)」に分けて計算しています(小数点第2位以下を四捨五入)。生まれ月による人数の差は補正しています。
<男子>
遅生まれ・春 1
遅生まれ・夏 2.1
遅生まれ・冬 1.1
早生まれ 0.8
<女子>
遅生まれ・春 1
遅生まれ・夏 4.4
遅生まれ・冬 0.5
早生まれ 1.6
早生まれは、男子に関しては0.8とやや不利に見えますが、女子は1.6とむしろプラスの結果となっています。
医学部のデータでも早生まれの不利は消失
続いては、旧帝大医学部のある1学年の生まれ月データです。
4〜6月 24人
7〜9月 30人
10〜12月 21人
1〜3月 21人
こちらは単純に人数だけのデータになります。7〜9月が多いですが、少なくとも中学受験のように、早生まれだから圧倒的に不利ということはありません。大学受験、しかも旧帝大医学部においても、早生まれのデメリットはほぼ消失しているといっていいでしょう。
次のページへ早生まれの子を持つ親が知るべき「勝負のかけどき」