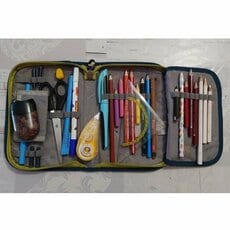共働き世帯の増加などにより、放課後児童クラブ(いわゆる学童保育所)の待機児童数は年々増加しています。学童に入れない、あるいは運よく入れたとしても、子どもが「行きたくない」と言い出すこともあるようです。子どもの放課後の居場所は、学童のほかにどんな選択肢があるのでしょうか? 学童保育の運営者をサポートする「あい和学童クラブ運営法人」代表・萩原和也さんに聞きました。※別記事<「ぎゅうぎゅう詰め」の学童が増えている 人口の多い都市部で“学童待機児童ゼロ”の自治体があるのはなぜ?>から続く
【表】待機数児童数ワースト20の自治体は?(ほか自治体別データ全5枚)「子どもの放課後」の居場所、公設学童以外の選択肢は?
――待機児童をまぬがれたとしても、「ぎゅうぎゅう詰め」の学童で子どもがストレスを抱えたり、性格に合わなかったりして「行きたくない」となる心配もありそうですね。
公設の学童保育所の場合は、数少ない広域学童を除けば原則として子どもが通う小学校の学区にある施設しか利用できません。また運営の方針も地域によって本当にさまざまです。その学童が本当に子どもや保護者に合うかどうか、実際に入ってみないとわからないのが難しいところです。
――学童に入れない、あるいはやめたいとなった場合、子どもの放課後の居場所には、ほかにどんな選択肢がありますか?
子どもの放課後の居場所について、主な選択肢をいくつか挙げてみます。
1)放課後子供教室
文科省が行う子どもの居場所を確保するしくみです。小学校の一部の教室や公民館などを活用して、放課後や夏休みなどにさまざまな学習・体験プログラムを実施しています。学童保育所は共働き世帯を対象としていますが、放課後子供教室は利用希望者すべてを受け入れ、無料か低額で利用できます。ただし、実施日が週に数日の地域も多く、夕方5時くらいまでしか利用できない自治体が多いです。
2)民間学童保育所
放課後児童健全育成事業を主目的としていない学童保育所で、学習塾やスポーツクラブ、計算塾、そろばん塾、ダンススタジオ、英会話教室などが事業を拡大して設置運営することが通常です。国の補助金の対象外ですから、利用者が支払う月謝は5~10万円になります。ただし縛りがない分、事業者が保護者にアピールしたい種々の事業を展開できるのが魅力です。
次のページへ児童館