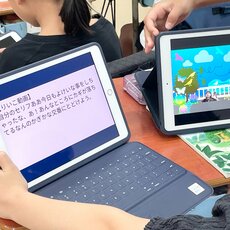子どもが小学校高学年くらいにさしかかると、口数が減ったり反発したり。親から見ると「ちょっとめんどくさい」のがこの時期です。「第二次性徴」とも言われるこの時期、脳やからだはどう変化するのか、大事にしたいことについて聞きました。子育て情報誌「AERA with Kids2024冬号」からご紹介します。
【マンガ】思春期になっても娘たちと仲がいい夫。なぜなのか娘に聞いてみると…?(全8枚)4年生くらいから、からだが変化してきます
学校から帰ってくるとゴロゴロ、こちらがなにか言うと反発。そんな様子に、ついイラッとして親子げんかが勃発……。小児神経科医の星野恭子さんは「からだと脳の面から見ると、4~6年生くらいの年齢は決して快適な状態ではないのです」と話します。
「まず、からだの成長とともに、二次性徴があらわれます。そして、脳もめざましく発達します。同時に脳内のさまざまなホルモンが大量に分泌されるので、脳内の大きな神経系も乱れがちになるのです」(星野さん)
めざましい成長に、脳もからだも戸惑っているような状態にあるのが、4・5・6年生。
「もちろん個人差があります。でも、これによって子どもは自分でもコントロールできないくらい感情の起伏が激しくなったり、しんどさを感じたりすることがあるのです。このような事情を親御さんは理解してあげましょう」
でも、この「乱れ」には出口がちゃんとあると星野さん。
「15、16歳くらいになると、前頭葉の発達も緩やかになり、同時にからだの発達スピードも落ち着いてきます」
そして、この時期の子どもたちに対して星野さんがいちばん心配していることが「睡眠不足」。
「忙しくなり、そのしわよせが睡眠に出てしまう子どもが圧倒的に多いのです。この時期に睡眠が不足しては、からだも脳も悲鳴を上げてしまいます」
健やかな成長のために、より「正しい生活リズム」を徹底したいのが4・5・6年生なのです。
【4・5・6年生の親が知っておきたい! 4つのキーワード】
1)第二次性徴
性ホルモンの分泌が活発になり、男子は精通のスタートや、筋肉が増えてからだつきの変化も見られるように。女子はからだが丸みを帯び、生理がはじまる人も。「そうなったときの準備など、親子で話し合っておきましょう」
次のページへ残り3つのキーワードは?