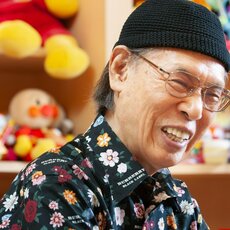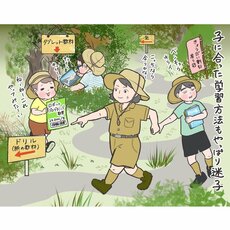日本酒や焼酎、みりんなど日本の「伝統的酒造り」が、ユネスコの無形文化遺産に登録されました。「こうじ菌」を使った日本独自の酒造りとは、どのようなものでしょうか? また今回の登録により、国内外での日本酒のブランド力がアップし、日本酒離れの歯止めにも期待がかかるといいます。小中学生向けのニュース月刊誌『ジュニアエラ2025年2月号』(朝日新聞出版)からお届けします。※前編<日本の「伝統的酒造り」が無形文化遺産に! 登録されるとどんなメリットがあるの? わかりやすく解説>から続く
【写真】「伝統的酒造り」のわざと「こうじ菌」はこちら(5枚)/日本のその他の「無形文化遺産」も「こうじ菌」を使い職人が手作業で酒造り
2024年12月に南米のパラグアイで開かれたユネスコ(国連教育科学文化機関)の政府間委員会で、日本酒、焼酎、泡盛、みりんなどの日本の「伝統的酒造り」が無形文化遺産に登録されました。これまで日本からは歌舞伎、和食、和紙などが登録されていて、伝統的酒造りは23件目になります。

伝統的酒造りは、カビの一種であるこうじ菌という微生物を使って職人が手作業で行う酒造りのことです。こうじ菌の働きにより原料である米や麦のでんぷんが糖に変わり、さらに糖からアルコールがつくられます。こうした過程が同時に進むのが日本の伝統的酒造りの特徴です。
欠かせないのはカビの一種「こうじ菌」
500年以上前に原型が確立した伝統的酒造りのわざは、こうじ菌からできる「こうじ」を使うという共通点を持ちながら、日本各地の気候風土に合わせて発展し、日本酒、焼酎、泡盛、みりんなどの製造に受け継がれてきました。
「伝統的酒造り」の主な特徴である、3つのわざは以下です。
1)原料を処理するわざ
米や麦などを蒸して、酒造りに適した状態に整えます。

2)こうじを造るわざ
蒸した米などにこうじ菌を入れ、繁殖させて「こうじ」を造ります。

3)発酵を管理するわざ
米などの原料にこうじ、水などを加えて発酵させ、酒の元となる「もろみ」を造ります。