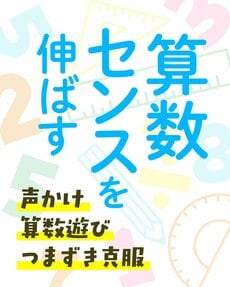――子どもの勉強のパフォーマンスを上げるために、親ができることはありますか?
親は「いかにペースメーカーになるか」が大切だと思います。息子の受験勉強中、私はタイマー付きの時計で時間を計り、30分ごとに5~10分の休憩を入れていました。これを何セットも繰り返して、合計すると休日には1日7~8時間は勉強をしていました。
集中力が続く時間は個人差が大きいものの、20~30分と言われています。また、記憶に残りやすいのは勉強の最初と最後、そして面白いと感じた部分で、それ以外は結構抜け落ちてしまいます。長時間ぶっ通しで勉強をしても、記憶から抜け落ちる部分が多くなりますから、短時間で区切る方法は非常に合理的です。それに、何も考えずにボーッとする時間も意外と大切なのです。私たちの脳は、眠っている時や、ボーッとしている時に記憶を定着させていると考えられています。
ホワイトボードを活用して、子どもに勉強を説明させる
――そのほか、受験勉強に効果的だった取り組みがあれば教えてください。
勉強で成果を出すには、テクニックを知っていることが非常に重要です。まずは「書いて覚える」を身につけさせるといいでしょう。例えば、漢字のとめ・はね・払いなどは実際に書かないと絶対に覚えられません。息子にも「どんな天才でも書かなければ覚えられない」と何百回も言いました。
それから、人に教える経験も勉強の理解を深めます。わが家ではホワイトボードを買って、算数の複雑な計算などを息子に説明させていました。なんとなく解いて数字が合うこともありますが、図を書いて理論を説明させると案外できないことも多いものです。私は、勉強は頭で覚えるのではなく「目で覚えるもの」だと思っています。脳のワーキングメモリーだけでは絶対に覚えられず、書くことによって目で覚え、手でも覚える。それを徹底させましたね。
――アウトプットすることが大切なのですね。
でも、もっとも効果があるのは、親も一緒に勉強することです。「模倣効果」といって、親が横で勉強をしているのを模倣して、子どもも勉強するようになります。私も息子の隣に座り、一緒に問題を解いていました。受験問題の算数は大人でも難しく、最後まで息子にかないませんでしたね。親としては大変かもしれませんが、勉強もコミュニケーションツールだと考えてはどうでしょうか。サッカーが好きな子どもはサッカーを、絵が好きな子どもは絵を話題にするように、勉強を親子共通の話題にするのです。
中学受験は“諸刃(もろは)の剣”で、親が勉強についてガミガミ言っていると子どもの人生がネガティブになってしまいますが、勉強をコミュニケーションツールにすれば親子のかけがえのない時間になります。親の仕事は塾のお金を出すことではなく、子どもと一緒にいることだと私は思っています。
(取材・文/越膳綾子)