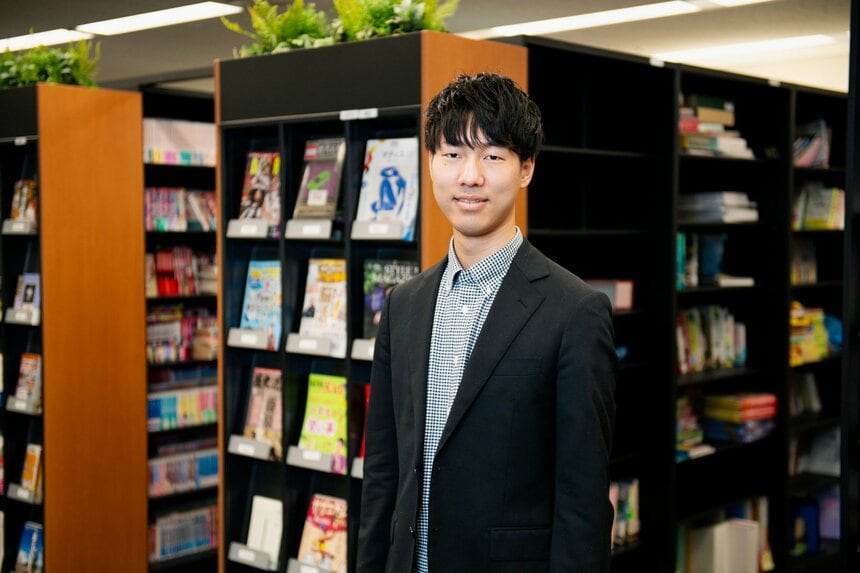読書離れが進むといわれる今どきの子どもたち。本を読んでほしいけれどなかなか定着しないというご家庭に、子どもが読書にハマるオンライン習い事「ヨンデミー」を立ち上げた笹沼颯太さんが、子どもを本好きにする方法をアドバイス! 今回は、本好きの聖地「図書館」をもっともっと活用するテクニックを伝授。本が読める子どもほど陥りやすい、注意点も聞きました。
【写真】開成高校出身・ぎん太さんの本棚はこちら学校の図書室&図書館をハイブリッド使い
――笹沼さんは、小学生のころは図書館をどんな風に活用していましたか?
僕は、地域の図書館にも行きましたが、学校の「図書室」のヘビーユーザーでした(笑)。本が好きだったり、ある程度読むスキルがあったりする子どもは、まず学校の図書室を活用する方が多いかもしれません。学校の中にあって移動もらくだし、勝手も熟知しているので探しやすく、借りやすいですから。
でも、流行や人気の本などが登場すると、借りる人が殺到してなかなか自分のところまでまわってこないという状況も多々あります。僕は、そういう本があるときは親に予約をしてもらって図書館に借りに行きました。
図書館は、本との出合いの場でもありますが、こんなふうに読みたい本が決まっていれば、事前に予約をして借りたり、ほかの図書館から取り寄せたりすることができますよね。僕が小学生のころは、オンラインで図書館の蔵書検索や予約をして、家の近くの貸し出し・返却専門のブースで受け取るということもよくしていました。
シリーズ本などは、学校の図書室では「〇巻と〇巻がない!」ということもしょっちゅうあります。そういうときも、図書館で探しては見つけていましたね。
地域の図書館を使い分けよう
―――図書館の予約システムをフル活用していたのですね。
そうなのです。僕が住んでいる地域は、中央にドーンと大きな図書館があり、まわりに小さな図書館がいくつか点在していました。大きな図書館は、新しい本や読みたい本を見つける自分の中のメイン図書館、もう一か所の小さな図書館はサブ的存在……こんなふうに使い分けていました。
次のページへ「学校の図書室」と「地域の図書館」、違いは?