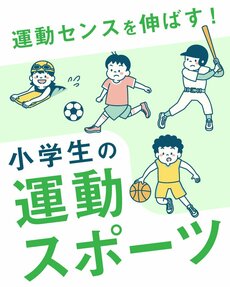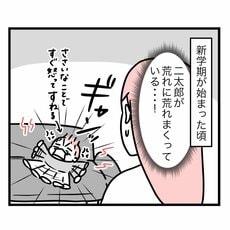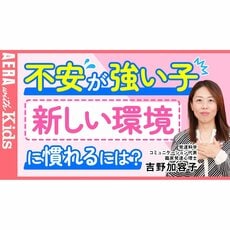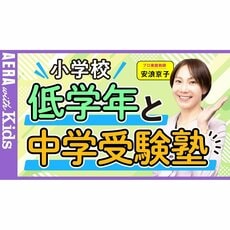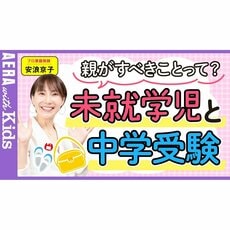もう一か所、駅前の小さな図書館は、先ほどお話ししたように予約した本を受け取り、返却するところ専門でした。そういえば、予約した本を仕事帰りの父によくピックアップしてもらっていました。こんな思い出も、読書の一部ですよね。
ヨンデミーのユーザーさんの中にも「自分が住む地域と、職場がある地域、両方の図書館カードを作っています」という方は多いです。図書館のストックが何ヶ所かあると、探している本が「ここにはないけれど、あの図書館にはある!」とスムーズに見つけやすいですよね。
――――学校の図書室と、地域の図書館の違いはどんなところでしょうか。
蔵書数や取り扱うジャンル、規模の違いはもちろんですが、本を取り巻く「空気」も全く異なると思っています。
ちょっと話がそれてしまうのですが、先日、ヨンデミーのスタッフと神保町(古本屋街がある町)に遊びに出かけました。神保町で古本屋さんをのぞくと、いつも出合うのが「一体だれが読むんだろう?」と思ってしまう、非常に「ニッチな分野」について語られている本たちです。でも、それが出版されて売られているということは、読者がちゃんといるということ。そこで「こういう本を読む人はどんな仕事をしているんだろう」「どんな場面を楽しむんだろう」とさまざまなことを考えるんです。
こんなふうに、自分がまったく手を伸ばさないであろう本を目にすると、「どんな人が読むんだろう、この本」と、その本を読む人のことを思い浮かべたり、想像したりするものですよね。これは「自分の知らない世界がこんなにあるんだ」ということを意識するきっかけにもなると思います。
そして、図書館ではまさにそういう本を「読んでいる」大人たちを目にすることがあります。子どもは、たくさんの読書家たちを前に「あんな本を読んでいる、すごい」と感じるかもしれませんね。こんな空気感は、図書館ならではです。
慣れている子どもこそ、意外と視野が狭まりがちなのです
―――本だけでなく、まわりにいる「人」の存在も読書意欲を刺激するのですね。
図書館で見かける読書家たちの存在は、大きな刺激になると思います。でも、ある程度本が読める、読むスキルがある子どもたちは、自然とエリアが決まってしまうものです。そこにちょっと注意したいですね。
―――エリアが狭まってしまうとは…?
図書館に慣れている子どもほど、無意識に児童書や図鑑のエリアくらいを見るだけになってしまいがちなのです。ですから、普段行ったことのないエリアにも足を伸ばしてみることをおすすめします。本の表紙や、タイトルだけを見るだけでもおもしろいですよ! 「こんな本があるんだ」「こんな世界があるんだ」という新しい発見があるかもしれません。
なにか「新しいこと知る」機会って、子どものうちは学校か家庭、習い事くらいですよね。そのほかにも「まだまだ知らないことがたくさんあるんだよ」と子どもに見せる、知らせる。図書館は、そんな活用のしかたもできるのです。
(取材・文/三宅智佳)