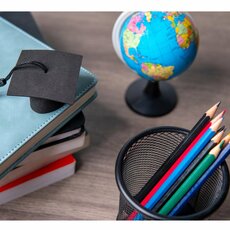そして、「あなたも今回、人のせいにしてしまったけれど、その良し悪しは置いておいて、人のせいにしたくなった気持ちがどう生まれてきたのかを確認してみよう」などと伝えてみてはどうでしょうか。起きたことを一緒に振り返って、お子さんが自分の気持ちを理解できるようにアプローチするのがポイントです。
もう一つ、長い目で見たときに親の対応として大切なのは、お子さんの自信を育むことです。自分の言動に責任を持ち、自分自身への信頼を育てることが、「人のせい」をやめることへの本質的な解決になります。
例えば、出発の時間ギリギリまで出かける準備をしないで、友達と約束の時間に間に合わず、相手を待たせるときに小さいウソをついてしまったとします。親御さんからすれば「間に合うならギリギリまで遊んでもいいけど、できなくてウソをつくならもう少し早く準備すればいいのに」と言いたくなりますよね。そういうときは、子どもを責めたりせずに「あなたがウソをついたり人のせいにしたりする理由は、こういうことが起きているからだよね」と解説してあげることが大事です。自分ができる範囲の約束や責任の負い方を子ども自身に認識させるということですね。
一方で、お子さんのキャパを超えた課題や責任が課せられていないかを見直してみてください。できないことが積み上がっていっぱいになって、一つひとつに向き合えずに人のせいにして逃げているのかもしれない。その場合は、負担を減らして一つ一つに向き合う余裕を作ることも有効だと思います。
(構成/布施奈央子)
※前編<お菓子を勝手に食べて「僕じゃない」と言う10歳男子 「ウソはダメ」の声掛けはあまり“効果がない”と専門家が話す理由>から続く
小川大介さん
※小川さんのYouTubeチャンネル「小川大介の『見守る子育て研究所®』」や、AERA with KidsのYouTubeチャンネルで、小川さんの話を動画で配信しています。