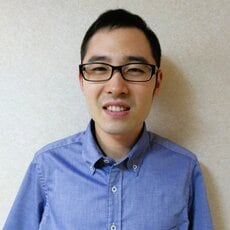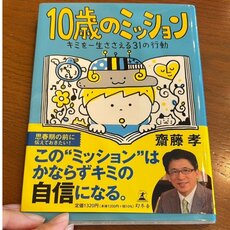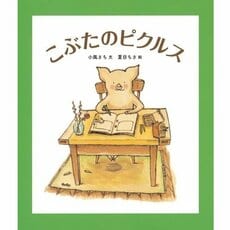多くの社会問題に真っ向から取り組み、共有することで解決への道筋をつける「リディラバ」を学生時代に立ち上げた安部敏樹さん。花まる学習会代表の高濱正伸さんとの対談では、「自分こそが社会問題そのものだった」と思春期を振り返り、率直に語ってくれました。「AERA with Kids」冬号からお届けします。
* * *
高濱 もう寒い時期なのに半袖のTシャツ姿ですか(笑)。
安部 僕の会社「リディラバ」のTシャツです。公に出るときはほとんどこれを着てアピールしてます。
高濱 リディラバの意味は?
安部 「Ridiculous things lover(バカバカしいことが好きな人)」が由来です。最初は仲間数人と始めたボランティア団体で、遊び心をもってなんでも楽しんでやろうと。
高濱 でもやっていることは、さまざまな社会問題の現場に足を運んでみんなで解決するという頼もしさ。しかもそれを事業、ビジネスにしたのがすごい。
安部 日本全国いろいろな現場に行きました。子どもの貧困、食品の大量廃棄、マイノリティーの労働事情、衰退産業、過疎化した村などなど、なんでもあり。社会問題ってそこらじゅうに転がっているけど、自分に関係ないと見えないし気づかない。まず必要なのは無関心の打破で、知ってもらうことから始めました。それが社会問題の体験ツアーで、学校なら授業や修学旅行、企業なら研修旅行として提案すれば事業として成立します。現場に行くことで初めて、他人の困りごとをみんなが自分ごととして共有できる。そのうえで対話を重ねて解決のための合意形成をし、資源を投入する。そのためにも法人化して、ツアーを扱える旅行業の資格をとったり、ジョイントベンチャーや新たな技術開発も始めた。省庁や自治体とも一緒に動くし、メディアも立ち上げました。必要なことはなんでもやる、金になるかどうかは二の次。だってうちはここまでしかできませんなんて一番ダサいじゃないですか。
高濱 そのセンスが最高だよね。事業の哲学、美学があるから、新たに行動を移すことに躊躇しない。でもたいていは自分の仕事はここまでと枠にはめこむんだ、そのほうがラクだから。そうすると自ずと組織も個も硬直化してしまう。それは心に響くのか、夢中になれるのかという熱い思いを行動規範にしていないと、いつの間にか枠だけで内面がなくなるんだよなあ。幼児期はなんにでも夢中になれるし、行動できるのに。
次のページへ掘って共有して、知恵や資源を投入しないと