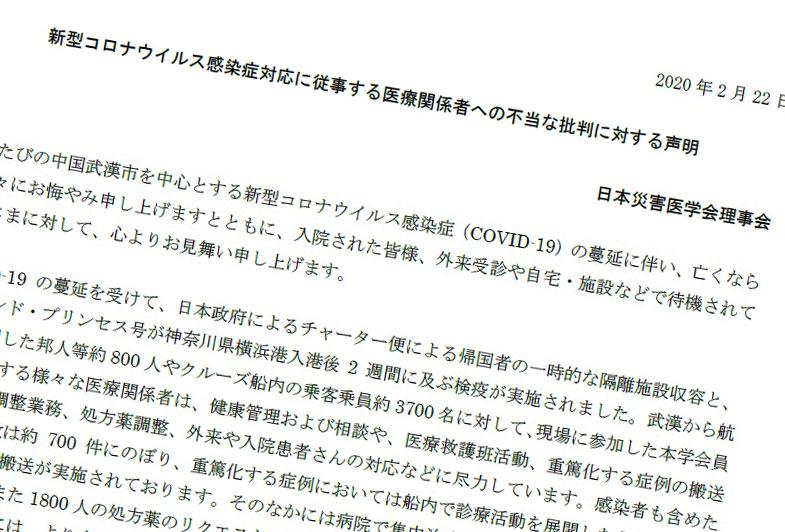
新型コロナウイルスによる形の見えない不安と重なるのは、9年前の原発事故での混乱だ。不安と恐怖という負の感情にどう向き合えばいいのか。AERA2020年3月9日号から。
* * *
東日本大震災で起きた原発事故では、福島県からの避難者が各地で差別と偏見に満ちた言動に苦しんだ。
福島県立医科大学「災害こころの医学講座」の前田正治・主任教授(災害精神医学)は言う。
「原発事故による放射線災害の状況と共通しているのは、第一に目に見えない災害だという点で、自然災害とはまったく違う様相を呈しています」
さらに、目に見えないことに加え、不安を増長させるほかの要因も、前田教授は指摘する。「ピークがいつ来るのかがわからない」ということだ。
地震や津波など自然災害の場合は、通常、発生時がある意味「ピーク」と言える。これに対して、放射能やウイルスの問題では、延々と不安や恐怖と闘い続けなければならない精神的な負担がある。その不安や恐怖が、正常なものなのか、病的なものなのかが判別しにくいことも、問題をさらに厄介にしている。
では、そうした感情とどのように向き合えばよいのか。前田教授はこう指摘する。
「一つのキーワードになるのは、『リスクコミュニケーション』です」
専門家、メディア、国民……。さまざまな立場の人たちが意見を交わして、いま直面しているリスクについて理解を深めていく、という考え方だ。
「リスクというのは、一方的に『こういうものです』と誰かが言って、それを受け止める、というものではありません」(前田教授)
そのリスクコミュニケーションの過程で重要だと前田教授が考えることがある。
「『リスクのトレードオフ』という考え方です。『こちらを立てればあちらが立たず』といった両立しない関係のことで、感染を心配しすぎても別のリスクが増えるかもしれない、ということを理解しておかなければいけません。特に、リスクを完全にゼロにしようとして極端な行動に走ると、別のリスクが生じやすくなり、場合によってはもともとのリスクより大きくなることもあります。向き合っていくしかないリスクもあるということです」




































