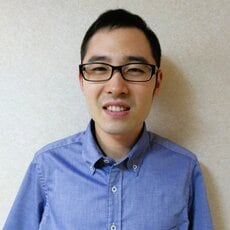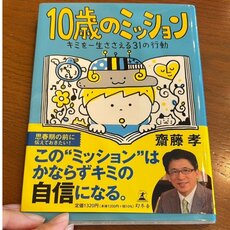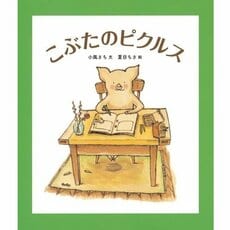アメリカには、13年ごと、17年ごとに大発生するセミがいる。どうしてそんなセミがいるのか。なぜ“素数”の「13」と「17」なのか。算数の頭も働かせながら、謎に迫ってみよう! 毎月話題になったニュースを子ども向けにやさしく解説してくれている、小中学生向けの月刊ニュースマガジン『ジュニアエラ』に掲載された記事を紹介する。

* * *
セミは卵からかえった後、幼虫として数年間を地中で過ごし、成虫になる直前に地上に出てくる。成虫の寿命は数週間だが、幼虫の期間は、例えばアブラゼミでは長くて6年ぐらいといわれている。
北アメリカの一部の地域には、アブラゼミよりはるかに地下生活の長いセミがいる。卵から成虫になるまで13年または17年もかかるのだ。しかも、その周期ごとにいっせいに大発生することから「周期ゼミ」といわれる。
なぜ、いっせいに大発生するのか。理由は、数百万年前~1万年前の氷河時代にあると考えられる。当時の北アメリカは繰り返し氷に覆われ、セミのすめる陸地は小さい島のように点々と存在するだけだった。成長に10年以上かかるようになり、仲間の数も減った。こうした環境では、毎年、バラバラに地上に出て成虫になるよりも、同じ年にいっせいに成虫になったほうが、オスとメスが出合って交尾する可能性が高まり、子孫を残しやすい。そこで、周期ごとに大発生するように進化したというのだ。
面白いのは、13年、17年という周期で発生すること。その間の14年、15年、16年などの周期のセミはいない。なぜだろう?
■大発生の周期がバラバラになると生き残りに不利!
13と17には“素数”という共通点がある。素数とは、表1のように、2以上の整数で、自分と1以外に割り切れる数を持たない数のことだ。だから、「周期ゼミ」のことを「素数ゼミ」ともいう。素数だと、何かよいことがあるのだろうか? 日本の生物学者・吉村仁さんは『素数ゼミの謎』という本の中で、17年ゼミを例に、次のような説を展開している。
氷河時代の北アメリカのある地域に、15~18年の周期ごとに大発生するセミたちがいた。それぞれが別々の年に大発生し続けていればよいのだが、問題は、同じ年に大発生し、交雑(※1)する可能性があることだ。交雑して生まれた子の周期は、親と同じになるとは限らない。例えば、15年ゼミと18年ゼミが交雑したら、生まれた子の周期は、親と同じ15年か18年ではなく、16年や17年などになる可能性もある。このように周期がバラバラになれば、一緒に地上に出る仲間の数が少なくなるから、出合いの機会は減って、子孫を残しにくい。つまり、周期の違うセミが同じ年に大発生し、交雑することは、生き残りにマイナスにはたらくと考えられるのだ。
(※1)交雑=同じ種ではないけれど、ごく近い種同士のオスとメスの間に子ができること。
■周期が“素数”だとバラバラになりにくい!
周期の違う2種類のセミが同じ年に大発生する現象が何年に1度起きるかは、二つの周期の数の最小公倍数(※2)で表せる。例えば、15と18の最小公倍数は90だから、15年ゼミと18年ゼミが同じ年に大発生するのは、90年に1度となる。そこで注目されるのが、素数は、ほかの数との最小公倍数が大きくなることだ。例えば、素数である17は、15との最小公倍数は255、18との最小公倍数は306だから、15年ゼミと17年ゼミの同時発生は255年に1度、17年ゼミと18年ゼミは306年に1度となる(表2参照)。これは15年ゼミと18年ゼミの90年に1度よりもかなり長い。つまり、周期が素数であるセミは、ほかの周期のセミと同時に大発生する確率が低く、周期がバラバラになりにくい。こんな状況が繰り返されるうちに、素数ゼミだけが生き残ったと考えられるのだ。
ところで、13年ゼミと17年ゼミが交雑することはないのだろうか? 吉村さんを含む日本の研究チームは、過去に13年ゼミと17年ゼミが交雑していた証拠を見つけ出したと発表している。そんな交雑が起こりながらも、13年と17年の周期はずれることなく、10万~20万年にわたって維持されてきたらしい。そこには、発生周期のカギを握る未知の遺伝子が関わっている可能性があると研究チームは述べている。
(※2)最小公倍数=ある整数を2倍、3倍、4倍……していった数を「倍数」という。そして、二つ以上の整数に共通する倍数を「公倍数」といい、公倍数のうちいちばん小さな数を「最小公倍数」という。5年生の算数で習う。
(文/上浪春海)
※月刊ジュニアエラ 2018年8月号より
![ジュニアエラ 2018年 08 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61UPIYClpLL._SL500_.jpg)