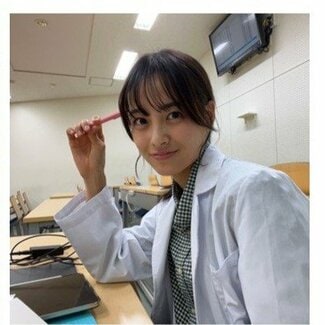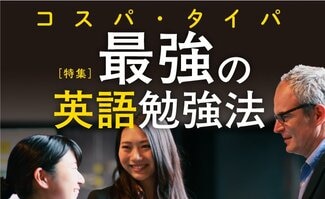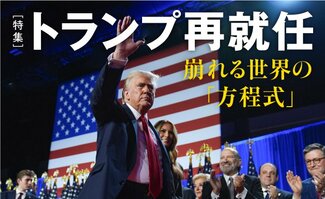新しい会社で働く人も多くなるシーズン。どの職場も「デジタル人材」が引く手あまたで不足しているという。ニュースでよく聞くけど、どんな人材で、どんな仕事をしているのだろうか。
* * *
転職サイトなどで最近、「デジタル人材」という言葉をよく見る。どの業界からも引く手あまたで不足しているという。明確な定義はないようだ。
「この10年くらいで大きく仕事の内容は変わり、すべてがデジタルになった」
と話すのは、エンジニアの派遣・紹介を手がけるフォーラムエンジニアリングの秋山輝之常務。秋山さんによると、もともとはプログラマーやシステムエンジニア、データを扱うエンジニアなどをIT(情報技術)人材と呼んでいた。
プログラマーは、特有のプログラミング言語を使い、システムやソフトウェアをつくる。システムエンジニアは、コンピューターのシステムの開発や設計をする。
たとえば、仕事を効率化するため、紙の資料の情報をコンピューターに入力してデータ処理する。そうした“デジタル化”のため、一般職員とデジタル関係のエンジニアが一緒に仕事をする時代があった。
いまは同じ人が両方の仕事をこなすか、少なくともデジタルのことを理解し、精通した人が業務を進める時代になった。デジタル分野と一般業務の垣根がなくなり、これらに従事する人を広く「デジタル人材」と呼ぶようになったという。
営業やサービス部門では、昔は対面で顧客と人間関係を築き、対応してきた。いまは顧客とのやりとりをデジタル上で行うようになった。
具体的には、AI(人工知能)が顧客やサービスについての大量のデータを解析し、そこから規則性や関係性を見つけ出す。そして最適な対応は何かを判断してくれる。営業やサービス部門の職員は、それを使いこなさないと仕事ができない。
かつては人が紙に書き込んだ資料のデータをじっくりと見て、比較し、一定の法則性がないかなど、分析していた。あるいは、データの属性をもとにグループにまとめ、ランキングにした。それがAIの機械学習により、人間が気づかなかったことまで見つけ出し、最適な答えを一気に導き出してくれるようになったという。
 浅井秀樹
浅井秀樹