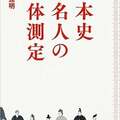「戦国三愚人」の一人に数えられながら、実は戦国時代の幕を開けた男がいた。細川政元は呪術に傾倒し、奇行で知られる一方で、将軍追放のクーデターを起こすなど、従来の政治構造を大きく変えた革命児でもあった。
実は政元は、織田信長よりも前に比叡山を焼き討ちした武将としても知られている。長年細川氏を研究してきた古野貢教授は、「様々な面で、織田信長の先例になった人物」と指摘する。
新刊『オカルト武将・細川政元 ―室町を戦国に変えた「ポスト応仁の乱の覇者」』(古野貢著)から一部抜粋して解説する。
* * *
比叡山を焼いた政元
政元が旧来の習慣や価値観に対して独特な態度を取ったという点で言いますと、信長と重なるところがあります。そのひとつは、旧来からの宗教的なものに対して容赦せず、他勢力に対するのと同じように例外なく対応したということです。実は細川政元も比叡山を焼いています(経緯については第5章で詳述)。
他にも歴史上有名な寺社への攻撃ですと、信長が本願寺と戦って、多くの寺院を焼いていますし、平清盛の子の重衡が、奈良の戦いで東大寺に火をつけたという話もあります。これについては彼の主体的な意思ではなかったとも言われていますが、大仏殿に向かって火を放ったのは事実で、当時の価値観からすればとんでもない振る舞いだったのは間違いありません。
室町時代を含め前近代社会においては、やはり寺院というものはその地域の重要な拠点ですし、御仏を扱っていることから侵しがたい場所として認識されていました。しかも仏教は本来、いわゆる現世利益――今生きている私が困っていることを解決してくださいとか、怪我を治して救ってくださいといったことなど――を叶える場所ではありません。現世(=生きている間)を真面目に一生懸命生きるので、死んだ後に極楽浄土へ行けるようにしてください、という声に応えるのが、仏教および寺院の役割だったのです。
「死んだ後に極楽へ行きたいんだったら、今を真面目に生きなさい」というのが仏教の基本的な教えであるわけですが、これが転ずると「寺に楯突いて余計なことをするなら、死んだ後は地獄へ行くことになるぞ」ということにもなるのです。
近代的な発想を持った政元
政元にしても信長にしても、このある種の脅しに屈せず容赦なく寺を焼くことができたことをみれば、彼らが既存の価値観にとらわれず、独自の価値観のもとに行動原理を設定した人物であったと言わざるを得ません。ですから近代的といえば近代的な発想を持っていたといえるのかもしれません。
ともあれ当時としては完全に常識外れですし、周囲から批判されるのも当然であったといえるでしょう。
『オカルト武将・細川政元』では、呪術や空中飛行の修行に没頭した政元の人生や、足利将軍を追放するクーデターの内幕など、応仁の乱以降の激動の時代を解説しています。