
「言葉の壁」解消以上の役割
消防団は、地震や台風といった大規模発生時に、仮設トイレの設置や段ボールベッドの組み立てなど、避難所運営の支援活動を行う。
避難所では、外国人は生活習慣や信教の違いから、日本人との軋轢が生じることもある。
たとえば、ムスリムは豚肉や、微量のアルコールが含まれるしょうゆなどを食べることができない。炊き出しを口にできず、ゼラチンやラード、ショートニングといった豚由来の成分が入っている可能性のあるパン類も食べられない。これを「わがまま」ととらえられれば、険悪な雰囲気が生まれ、分断が生じかねない。
外国人消防団員の役割として「言葉の壁」の解消が挙げられるが、スマホなどの翻訳機能でかなりのことができるようになった。今、切実に求められているのは、彼らの体験をもとにしたコミュニケーションの円滑化だという。
「自身もさまざまな困りごとに直面してきた外国人消防団員は、日本人、外国人、双方の気持ちを理解できる。だからこそ、誤解や対立を避け、両者をつなぐこともできるはずです」(中西さん)
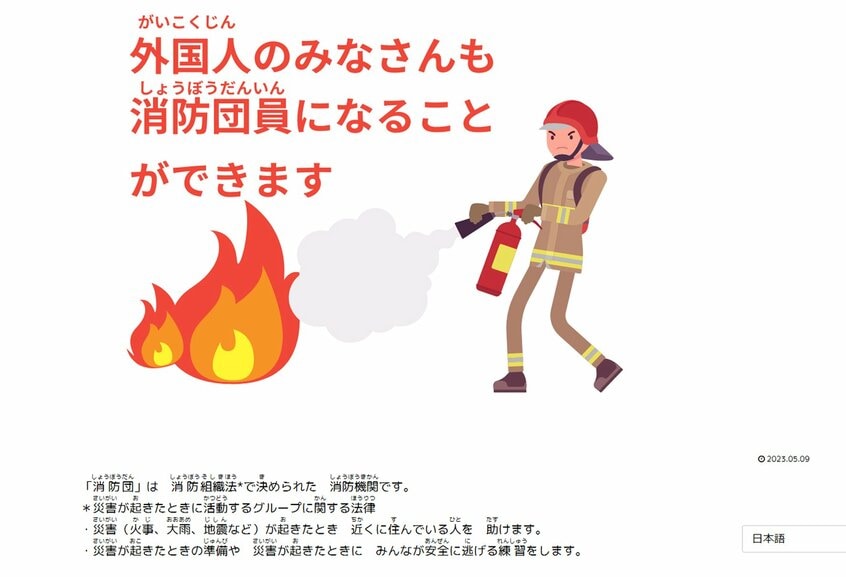
根強い外国人団員への反発
消防庁によると、全国の外国人消防団員数は582人(昨年4月1日時点)。20年と比べて約2.2倍になった。外国人機能別消防団の導入について、中西さんはさまざまな自治体から相談を受けてきた。
「『どうしてすんなり外国人の消防団をつくれたんですか』とよく聞かれます」
外国人が消防団員となることへの反発は一部にいまだ根強くあるようだ。
「草津市の場合、反対のパブリックコメントは数件だったと聞いています。でも、他の自治体では『消防団を外国人に乗っ取られる』とか、反対意見も多いそうです」
消防団は地域に根差した組織だ。「伝統を守ろう」という言外の意識と、「多文化共生」がうまくかみ合っていないのではないかと中西さんは推察する。
記者は長年、地域の防災活動に携わり、避難所運営も経験した。さまざまな事情を持つ避難者が続々と訪れるなか、待ったなしの判断が求められた。在留外国人が増えるなか、外国人消防団員の存在は不可欠なものとなっていくのではないだろうか。
(AERA dot.編集部・米倉昭仁)





































