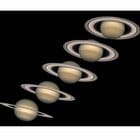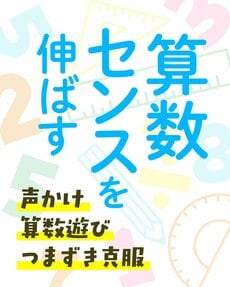アスファルト道路でよく見かけるカマキリですが、実は“ある虫”に操られていることが多いって知っていますか? さらに最近、人間によって自然環境が変化したことで、カマキリとその虫にとって、“想定外の事態”が起きていることがわかりました。京都大学生態学研究センターの准教授や大学院生による実験を見てみましょう。小中学生向けニュース雑誌「ジュニアエラ2025年2月号」(朝日新聞出版)から紹介します。
【苦手な方は注意】アスファルト道路で死んでいるカマキリとハリガネムシの写真はこちらカマキリを操る「ある虫」の驚きの生態とは?
秋に道端でうっかりカマキリを踏みつぶすと、腹から細長く黒っぽい虫が出てくることがある。太さ1~2㎜のこの虫は、カマキリの寄生虫として知られるハリガネムシだ。
ハリガネムシは、産卵期の成体と受精卵、幼生は水の中で生活するが、その後は昆虫に寄生(ほかの生物の体にすみつき栄養をもらって生きること)して生きていく。ほかに、カマドウマ、バッタ、コオロギなどにも寄生する。
秋、メスのハリガネムシは水中でオスから精子を受け取り卵を産む。1~2カ月ほどで体長0.1㎜ほどの幼生がかえり、ほかの餌と混じってカゲロウやユスリカなどの水生昆虫の体内に入る。昆虫の腹に入った幼生は、シスト(一時的な休眠状態)になる。春になり、水生昆虫が羽化して水辺を飛び回り、カマキリに食べられると、シストから目覚め2~3カ月かけて成長し、カマキリの腸管の中で長さ10~40㎝のハリガネムシになる。そして再び秋になり、ハリガネムシに操られたカマキリが水辺にやってきて川に飛び込むと、体内からハリガネムシの成体が出てくる。このようにしてハリガネムシは、数カ月にわたる寄生生活を終え、生まれた川に戻ってくる。
ここで面白いのは、カマキリなどに寄生したハリガネムシが、宿主(寄生される側の生物)を「操る」という点だ。ハリガネムシは、自分の生まれた水中に戻り産卵するために、秋になるとカマキリなどの宿主を操って川など水のあるところに飛び込ませるのだ。

では、どういうしくみで宿主は水に飛び込むのだろう?
これまでの研究で、カマキリが水面から反射する光に多く含まれる「水平偏光」という特殊な光に誘われて飛び込むことがわかっている。人間は水平偏光を目に感じないが、カゲロウやアメンボなどの昆虫は、水平偏光を感じとることができる。ハリガネムシは、カマキリが水平偏光に引き寄せられるように操って、水に飛び込むという行動を引き起こさせているように見える。見た目には黒っぽく細長いだけのハリガネムシの、どこにそんな能力が潜んでいるのだろうと、驚かされる。
次のページへカマキリがアスファルトを歩くのはなぜ?