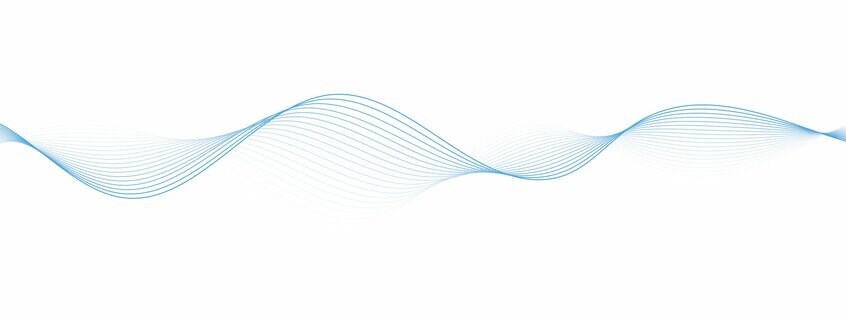
仕事や家事のとき、音楽をかけると歌詞が気になって作業に集中できない……そんな人はいないだろうか。音楽そのものを楽しみたいときも、日本語だとついついその意味が気になってしまう。小説家の榎本憲男さんもそのひとり。そんな榎本さんが魅せられた「音声だけの歌」を、ご本人のコラムでご紹介します。
* * *
「努力ではなんともならなかった」音楽と、その先にあった出会い
小説家を名乗る前、僕はながらく映画業界で働いていた。多くの技術者が各自の技術を持ち寄って映画は完成される。当時僕は、「音楽系の人にはやさしいね」と仲間から言われることがちょくちょくあった。「そんなことないよ」と返してはいたが、身に覚えがないことはなかった。
「好きこそものの上手なれ」とは言うものの、努力ではなんともならないものはある。そのことを痛感したのが音楽だった。それでも往生際悪く、昔はDJをやったり、今はオーディオ装置をいじったりして、アクティブに音楽と関わろうとしてはいる。ただ、演奏や曲作りとなると、もうお手上げだ。身分不相応な高価なギターを購入し「これだけ投資したんだから、必死に練習して上達するだろう」と意気込んだこともあったが、そのGibson175Dは数年後に友人の手に渡った。好きだから、人一倍聴く。すると耳が肥えてくる。そして、自分のパフォーマンスの低劣さにがくぜんとする。このサイクルをなんどもくり返した。人一倍音楽が好きなくせにまったく才能がないので、コンプレックスが憧憬(しょうけい)に変わり、さらに尊敬に発展した結果、音楽家、ミュージシャンと名乗る人には一目置くようになったのである。
2007年頃、僕は中国映画の製作に関わり、安田芙充央(やすだふみお)という作曲家兼ピアニストに出会った。知り合った時、僕は彼のことを知らなかった。その理由は、安田が主にドイツを中心にヨーロッパで活動していたからだ。安田はドイツのレーベル、ウインター&ウインターからから計21枚のリーダーアルバム(このほかに参加アルバムが11枚ある)を発表している。安田の特長は、クラシック音楽の技法に立脚しながら、ジャズ的な要素も織り交ぜ、独自の音や和音や音色を徹底的に模索することにある。




































