
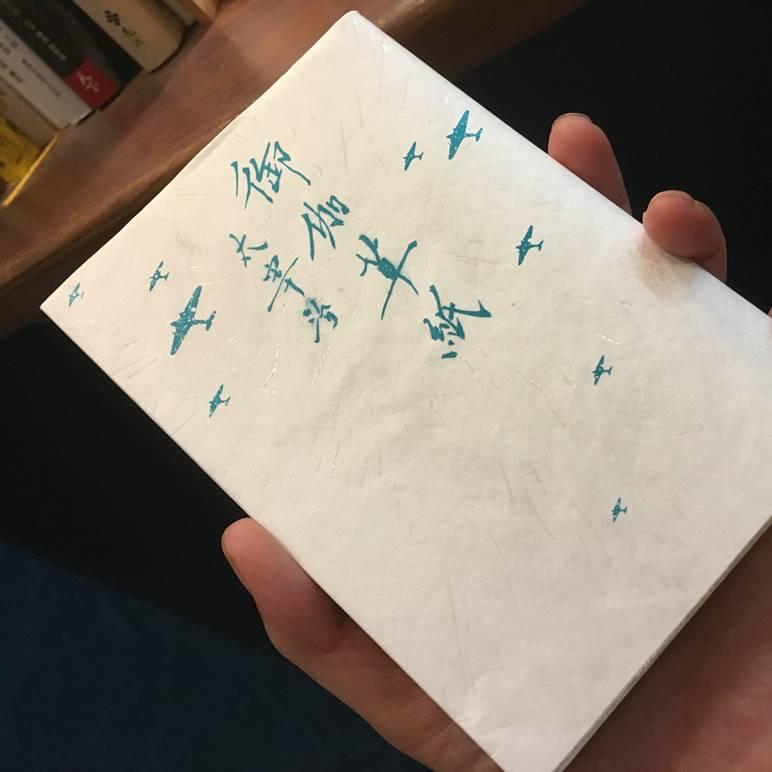
元朝日新聞記者でアフロヘア-がトレードマークの稲垣えみ子さんが「AERA」で連載する「アフロ画報」をお届けします。50歳を過ぎ、思い切って早期退職。新たな生活へと飛び出した日々に起こる出来事から、人とのふれあい、思い出などをつづります。
* * *
初の台湾(台南)で驚いたことの一つが「外食文化」。言葉は聞いていたが、具体的にどういうことかピンと来ていなかった。せいぜい、朝食から夕食まで気軽に外食できる店が充実、しかも安くてウマイらしいという程度の認識。そんな中、台湾っ子のリアルな食生活を垣間見る出来事があり、なるほどそういうことかと膝を打ったのである。
ある晩、家を借りていたホスト家族から「よかったら今晩うちに来る?」とご招待の連絡。単身で計画もなくノコノコやってきた私を不憫に思われたのであろう(それにしても台湾の方は実に驚くべきレベルで親切である)。
夕方、車で迎えに来て頂き、まずは台南最大の「夜市」の屋台へ。すごい人出だ。食べたいものがあれば言ってねと言われ、幾つかのお店で見たことない何かを買い、それを抱えて一同お宅へ。テーブルで待っていると、先ほど買った屋台料理がおしゃれなお皿に盛り付けされて登場。料理の説明を受けつつ、みなでワイワイ美味しくいただく。実に楽しい夜であった。
だが実は私、お宅にご招待いただいた時点で、勝手に「手料理をご馳走になる」と想像していたのである。それがまさかの屋台メシオンリー。しかしこれがなかなかいいのだ。お金も手間もかかっていない分、招かれる方も余計な気を使わなくていい。そして招く側も罪悪感や言い訳など一切なし。「これ美味しいよ~」と自慢し、「ホント美味しい!」と言うと実に嬉しそう。
で、我が国を振り返る。デパ地下、スーパー、コンビニ。持ち帰りのおかずはいくらでも売っているが、買う側にはいくばくかの罪悪感がつきまとう。友達を招待してデパ地下惣菜ってのもあるようでない。この差は一体何だろう。
その話を友達にしたら、誰が作ったか不明なのが嫌なのかもと。台湾のそれだったら、隣のおばちゃんにおすそ分けしてもらうみたいでいいナと。なるほど台湾の店はどこも小さくて、売ってるおばちゃんが作る人である。外食文化とは、街が丸ごと大家族という顔の見える関係の賜物なのだ。
※AERA 2019年7月29日号






































