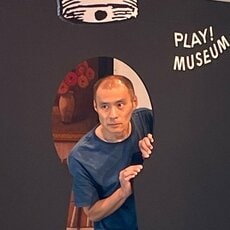そして何より、「悔しい」と思った気持ちを安心して言葉にできる。そんな“感情のゆれ”を受け止める家庭の雰囲気が、子どもにとっての安全基地になります。何か正しい答えを与えようとしなくても、ただ気持ちを受け止めてくれる大人がそばにいるだけで、子どもは少しずつ前を向く準備を始めます。
無意識のうちに子どもにプレッシャーを与えていることも
そしてもうひとつ大切な視点があります。「どこまで頑張らせていいのか?」という問いを、保護者が自分自身に問い続けることです。子どもが一生懸命に取り組む姿は、保護者として誇らしいものです。ただ一方で、「もっとできるはず」「やるからには最後まで頑張らなきゃダメ」という空気が、無意識のうちに子どもにプレッシャーを与えていることもあります。
時には、「無理して続けなくてもいいんだよ」「やめても大丈夫だよ」と伝えることが、人生を長い目で見たときに、大切な支えになることがあります。「頑張らないと価値がない」ではなく、「そのままのあなたでいることが大切」と感じられる家庭の中でこそ、子どもは本当の意味で安心して挑戦し続けることができるのだと思います。
スポーツの現場の仕組み、そのものを変えていく必要がある
研究者としてこのテーマに向き合うとき、いつも思うのは、保護者・家庭だけで背負いきれないケースがある、という現実です。頑張って練習していても試合に出られなかったときに保護者が「応援していたよ」「声が出てたね」と伝えても、本人の中には「どうして自分は出られないの?」という悔しさが残ってしまうことがあります。そしてそれをうまく言葉にできず、家庭にピリピリした空気が流れることも。このような感情のゆらぎを、“家庭の努力だけ”で抱え続けるのは、保護者にとっても子どもにとってもつらいことです。
だからこそ、スポーツの現場の仕組みそのものに「ゆらぎを受け止める余白」を持たせる必要があります。
次のページへ子どもにはプレーする「権利」がある