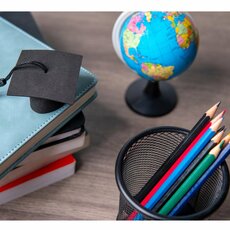1位は、生涯にわたって学び続ける能力を育むことを教育の主眼に
1位に選ばれたのは、市川(千葉県市川市)です。1937年に男子校として開学し、2003年に共学化しました。建学の精神の一つとして「第三教育」を掲げています。家庭教育を「第一教育」、学校教育を「第二教育」とし、それらと並行して自ら学ぶ自分自身による教育を「第三教育」として、生涯にわたって学び続ける能力を育むことを教育の主眼としています。文部科学省のSSH(スーパーサイエンスハイスクール)指定校として、理系生徒は高校2年次に全員が少人数で課題研究に取り組む「市川サイエンス」の授業を履修し、自分の興味関心からテーマを設定し、実験を繰り返して研究を深めます。年3回校内発表の機会を設けているほか、校外での発表会にも多く参加しています。文系生徒の課題研究として「LA(リベラルアーツ)ゼミ」も開講され、少人数で主体的に学ぶゼミ形式の授業で調査や議論を行い、各ゼミの最終回では全員が研究成果を発表します。

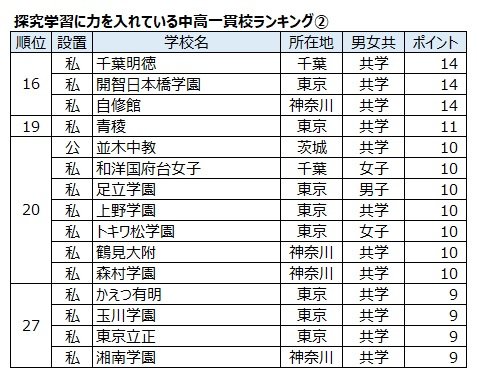
2位は、中1から高2まで学年ごとの探究プログラムを実践
2位には、開智未来(埼玉県加須市)が選ばれました。探究型教育やフィールドワークに定評があり6位にランクインしている開智(さいたま市)と同じ学校法人が、2011年に開設した共学校です。カリキュラムポリシーとして「探究型授業、FW(フィールドワーク)、探究型行事を通し生徒が主体的に学ぶことを支援し『想像力』『発信力』『思考力』を育成する」ことを掲げています。中学1年次の「里山探究フィールドワーク」や中学2年次の「British Hills探究フィールドワーク」など、中1から高2まで学年ごとに探究プログラムを設定。毎年2月に行われる「未来TED」は、1年間の探究学習の集大成ともいえるイベントで、中1から高2までの全生徒が集まり、1年かけて決定された各学年の代表生徒が日本語や英語でのプレゼンテーションで競い合います。
3位は、栄東(さいたま市)です。1978年に男子高校として開校し、1992年に中学校が開校、1994年に共学化しました。課題研究やグループワーク、ディスカッション、プレゼンテーションなど、生徒の能動的な学習を取り込んだ授業の総称としてAL(アクティブ・ラーニング)を導入し、教育の根幹に据えています。
次のページへ探究学習でどんな可能性が広がる?