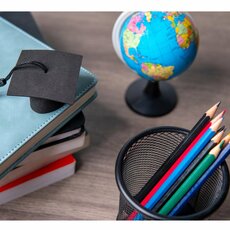2)やることを「選択制」にして行動を促す
子どもの行動を起こすには自ら「やりたい」と思ってもらうことも大事。それなら、やることを「選択制」にして、本人に選ばせることでやる気を引き出す方法もあります。例えば宿題で、音読と算数のプリントがあったとしたら「どっちからやる?」と聞いて選んでもらいましょう。または、「アイス食べてからやる? やった後にアイス食べる?」など、楽しくなるような選択肢を用意するのも効果的です。
<取り組みやすくなる声かけの例>
「どっちの宿題からやりたい? 自由に選んでいいよ」
「音読、どこからやろうか?」
「片付け、コレから片付ける? アレから片付ける?」
「ゲームやってから片付ける? お母さんと一緒に今から片付ける?」
――ゲームをやってから宿題やると言ったのにやらない! というケースもありがちですが、そういう場合はどうすればいいのでしょうか。
行動を起こすときは、エネルギーがいるんです。人間の脳は車のエンジンに似ていて、車は50km/hになるまではけっこうアクセルを踏まないといけないけど、トップスピードに入ったらほとんど踏まなくても進みますよね。それと一緒で、いかにスムーズに軌道に乗せるかが大事。ですから、最初の部分を手伝ってみてはいかがでしょう。お子さんと一緒に座ってランドセルから宿題を出して、1問目はなんなら親御さんが先導して解いてもいい。2問目、3問目からお子さんにやらせるという感じでやってみてください。
擬音語、擬態語で興味をくすぐる
――まだ低学年のお子さんだと「宿題ヤダ!」みたいな答えが返ってくることもありますね。
「宿題」というワード自体に拒否反応を示すこともありますよね。そんな時は、擬音語や擬態語を使ってみてください。特に年齢が低い子は、「宿題やる? それとも数字カキカキする?」と言い換えると「カキカキ? 面白そう!」とやる気になってくれたりします。食事など別のシーンにも使えます。ごはんを全然食べない子には「ごはんにする?パンにする?」を「ごはんにする? パンパンにする?」なんて言ってみたりすると「パンパンってなに?」と、ちょっと楽しくなると思います。普通のパンを出すんですけどね(笑)。子どもの行動が起こりやすくなるような、楽しい工夫をしてみましょう。
ただ、一つのことを集中して行うことが好きなお子さんは、定番の聞き方のほうが安心するということケースもあるので、そこは気をつけてください。
(構成/布施奈央子)