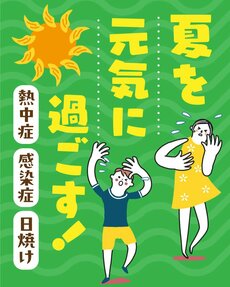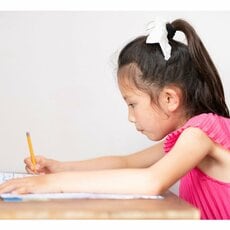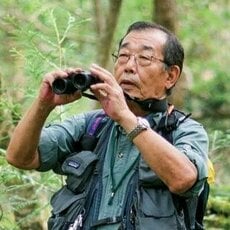例えば、子どもたちがいちいち職員におうかがいを立てて行動していたら、そこは大人が子どもを管理・統率している窮屈な学童である可能性があるので要注意です。逆に、スペース的には多少ぎゅうぎゅう詰めでも、子どもたちが楽しそうに過ごしていたら、そこは自主性を重んじるよい学童のように思います。また、周りの先輩保護者からの情報収集も有効です。
学童の施設内が比較的、整理整頓されていることもポイントです。また「~は禁止」「~はダメ」という抑止的な張り紙が少ないこと、何よりその学童の職員たちが楽しそうに働いているかどうかを、見学の際に確認してみるとよいでしょう。
――大規模化で起きるトラブルとは、どのようなものですか?
ちょっと想像してみてください。通勤ラッシュの電車の中に2時間も3時間も閉じ込められていたら、大人だってイライラしたりいざこざが起こったりしかねませんよね。
学童もそれと同じような状態です。イライラした子どもたちがささいなことでケンカをしたり、職員の指示に従わなかったりする子もいます。
現場の職員もまた大多数の子どもの対応で疲弊し、長続きしません。特徴的なのは「突発性難聴」になる職員が多いことです。子どものやや高いトーンの声が満ちあふれた空間で何時間も作業していると、耳がやられてしまうのです。
――せっかく入った学童で、それは頭が痛い問題ですね。
それなら児童の数だけ職員を増やせばいいじゃないかと思うでしょうが、学童保育に出ている補助金はそれほど多くなく、職員の手当ても安いため、なり手がいない。職員がころころ変わるため、子どものトラブルについての引継ぎも行われなかったりします。子どもにとっては慣れた大人がすぐいなくなってしまうので、さらなるトラブルや行き渋りにつながっていきがちなんです。
萩原和也