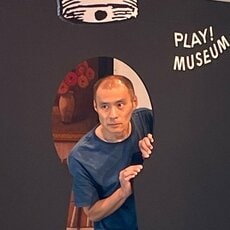――スポーツ系の習いごとは人気がありますが、それでも身体能力が低下しているのですね。
もちろん習いごとのスポーツも運動ですが、例えば「週1回のサッカー教室でドリブルの練習をする」といったように、決まった時間内に特定の運動をすることになりがちです。子どもたちが山を駆け回っていた時代のように、坂道を上って下って木に登り、川も渡る……といった複合的な体の使い方とは違うと思うんですね。
現代では、何かをするための「コスパ」や「タイパ」を気にする風潮がありますが、「何のため」というわけでもない日常的な外遊びでの動作が、その後に影響を与えていたのかもしれません。
小学生のうちに「骨量」を増やしておくことが大事
――子どもの骨は、何歳ごろからいつまで成長するのでしょうか。
骨量は思春期からぐんぐん増加して、女子は16歳ごろ、男子は18歳ごろにピークに達し、その後増えることはありません。女性は閉経前後に骨量が急減し、男性は70歳ごろから減っていきますから、子どもの生涯のことを考えても、小学生時代に骨を育てることは非常に大切です。
――子どもの骨を丈夫にするために、家庭でできる対策を教えてください。
まずは、毎日の食事でカルシウムとビタミンDをとることを意識していただきたいですね。骨は、「破骨(はこつ)細胞」が古くなった骨の細胞を壊し、「骨芽(こつが)細胞」がカルシウムなどを吸着して再構築するサイクルを繰り返しています。ビタミンDはこの仕組みをサポートしてくれます。
カルシウムと言えば牛乳を思い浮かべる人は多いかもしれませんが、これまでの研究では牛乳が骨を丈夫にするという報告もあれば、そうではないという報告もあり、結論が出ていません。牛乳に限らず、さまざまな食品からカルシウムを摂取するといいでしょう。小魚はカルシウムとビタミンDの両方が含まれているので、子どものおやつにおすすめです。
ビタミンDはキノコ類などにも含まれていますが、食事からとることが難しく、日本人の子どもに不足している栄養素です。しかし、日光に当たると体内で合成されるので、外を散歩する時間を設けるなどするといいでしょう。夕方の木漏れ日や、朝の爽やかな日差しを浴びるくらいでも十分です。
次のページへ適度な運動負荷をかける