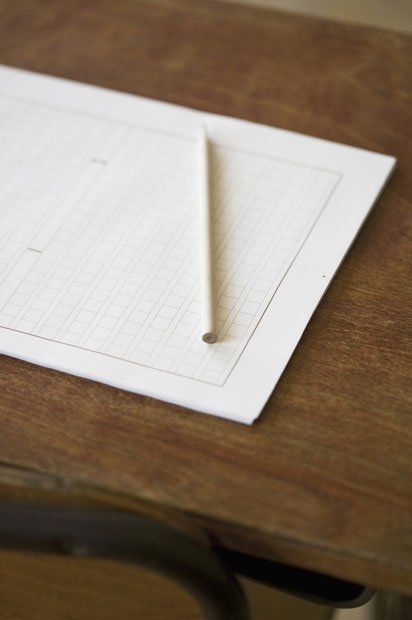
数値目標を掲げ国際化を標榜する大学に毎年、億単位の資金を支援する。国のそんな制度に選ばれたキャンパスで、実際に起きていることとは?
入学直後の英語のテストでは、だいぶ手を抜いた。早稲田大学スポーツ科学部3年の男子学生は、先輩からこうアドバイスされていたからだ。
「あれはまじめにやるなよ。楽しく単位を取りたいならね」
テストは、必修科目の英語の授業「General Tutorial English」のクラス分けに使われる。学生4人を教師1人が受け持ち、会話は英語のみ。「グローバル人材」の輩出を掲げる早稲田の目玉授業の一つだ。
「テストで手を抜くのは、能力相応のクラスだと難しくなるから。単位は落としたくない」
と男子学生。すべての学生がグローバル志向とは限らない。
逆に、国際教養学部1年の女子学生は、授業が予想より日本的で少し期待外れだったという。米国で暮らした経験があり、英語は堪能だ。
「ばんばんディスカッションするのかと期待していた。少数だが英語力の乏しい先生もいて、易きに流れる学生も目立つ。活気がばらついている感じ」
国際化を目指す大学を文部科学省が重点支援するスーパーグローバル大学(SGU)創成支援事業は2014年に始まった。世界ランキング100位以内を目指す「トップ型」は、早稲田と慶應義塾、旧7帝大などの計13大学。取り組みに特色がある「グローバル化牽引型」は24大学で、計37大学が選ばれた。




































