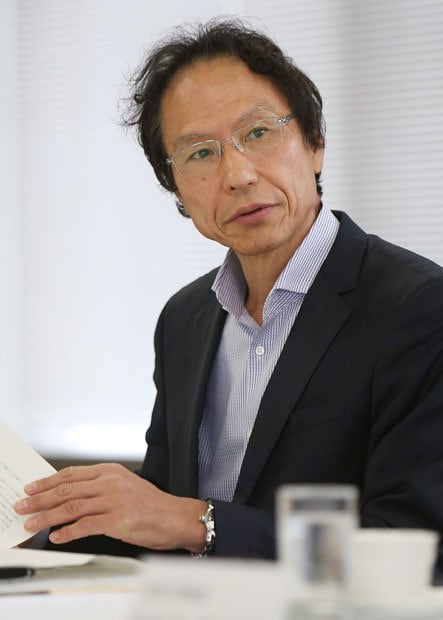
政治学者の姜尚中さんの「AERA」巻頭エッセイ「eyes」をお届けします。時事問題に、政治学的視点からアプローチします。
* * *
このコラムの執筆時点(8月7日)ではどうやら、かつての安倍首相の時の談話に匹敵するような「戦後80年談話」が石破首相の口から発せられることはなさそうですが、石破首相の「見解」という形で、先の戦争について自分の思いの丈を語ることになりそうです。
それにしても、戦後80年という節目の年に戦争と敗戦、そして戦後復興について来し方行く末を国の操舵を預かる最高権力者が語ることに、さほどの盛り上がりを感じられないのはどうしたことでしょうか。米国の著名な日本研究者のキャロル・グラック氏は、第2次世界大戦終結後の長い時間のスパンを、「戦後」という歴史の尺度ではかり、それに特別な意味を込めてきたのは、日本だけではないかと指摘しています。おそらく、ドイツもイタリアも、そうした時間のくくり方が、半ば「公定」の歴史になってはいないはずです。にもかかわらず、日本ではそうではなかったのはなぜなのか、この点は検討に値するテーマではないでしょうか。
察するに、昭和−平成−令和と続く「戦後」という時空間は、国民にとって近代日本の歴史の中で最も心地よく、繁栄とカッコ付きの「平和」に満たされていたからではないでしょうか。
何よりも日本はこの間、世界有数の経済大国になり、敗戦直後、誰も予想しなかったような国際的な地位を獲得しました。こうした意味で「戦後」という歴史のくくりは長らく国民に受け入れられてきたのだと思います。
しかし、冷戦崩壊から30年余り、戦後の繁栄と平和という「既得権益」が縮小し、「戦後」あるいは戦後民主主義が、「保守」のイメージと結びついているとしか感じられない世代が台頭したことにより、「変化」を、さらに既得権とその秩序の「改造」を求める声が大きくなっています。それは、今回の参院選での新興政党の著しい台頭を見れば、明らかです。
果たして「戦後」という歴史のくくりが、このまま野垂れ死にするような結果に終わるのか、それとも「戦後」という歴史のくくりが新たに甦るのか。8月15日の迎え方によって、その帰趨を占うことができるのではないでしょうか。
※AERA 2025年8月25日号
こちらの記事もおすすめ 「保守、極右などが混在する包括型政党としての自民党優位時代の終了 『比較第一党』となった石破政権の進む道とは」姜尚中






































