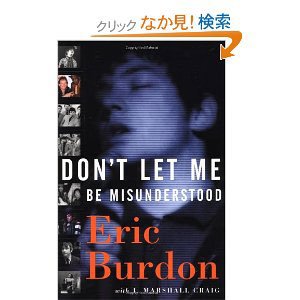
■本書(第4章Clear Horizon)より抜粋
1965年、ニューヨークで初めてラサーン(ローランド・カーク)に会った。彼が2週間、バードランドに出演していた時だ。俺は彼のレコードの熱烈なコレクターだった。だから、実物に会いたいと思っていた。
彼は人間離れしていた。つまり、野人で鬼才だった。初めてステージの彼を目の当たりにすると、彼は、ぼろを着たサムライのように見えた。鈍く光る金管楽器を何本も花づな状に首から吊るし、ワイヤーとピックアップとテープ・レコーダーを一緒くたにしてまとっていた――まさに“サウンド・ツリー”、彼が自称した通りだった。彼は、並はずれた演奏とサウンドで、彼の言葉を借りれば、“ブラック・クラシカル・ミュージック”というものを提供した。
数か月後の冬の午後、俺はジョン・スティールと、新しいレコードを物色するため、サム・グッディーズに向かっていた。すると、ラサーンに出くわした。彼は、店の外の曲がり角に立って、ペニーホイッスルを吹きながら踊っていた。彼は気前よく、その笛を配ろうとしていた。
俺は最初、ホームレスのストリート・ミュージシャンだろうと思った。だが、少し近づくと、テープでくっつけた3本のステッキと黒い顔、目が見えないことに気付いた。彼は、数フィート離れたところから、近づいてくる俺たちの声を聞き、すぐに誰だかわかった。
「おいおい、アニマルズだぞ。変わりないか? ビッグ・アップルでいったい何をやっているんだ?」と、彼が唸るように言った。
ジョンは一瞬、ぽかんとし、俺の顔を見た。
「おい、ローランド・カークだよ。信じられないな。やあ、ローランド」。
「俺は今、ラサーンと名乗っているんだ。ある晩、夢のなかで、ラサーンに名前を変えろという神のお告げを聞いてな」。
「ラサーン、その名前は好きだよ。いい響きだ」と言って、俺は、彼が差し出した手を上下に強く振って握手し、俺たちは抱き合った。
「どこへ行くんだ?」。
「サム・グッディーズにレコードを買いに行くんだ」。
「俺も行くところだ」。
彼は、片手で俺の腕を、もう一方でジョン・スティールの腕をつかんだ。そうして俺たちは、サム・グッディーズに入った。
テンプテーションズの曲が勢いよく、サウンド・システムから流れる店内で、黒人が一人、涼しい顔をしてタンバリンを叩いていた。ラサーンが、耳をそばだてた。彼は、レジにもたれて、こう言った。
「そのタンバリンの叩き方が気にいった。独特だ。俺と一緒にこい」。
俺たちはみんな、声を立てて笑った。タンバリンの奏者以外は。彼の名前は、ジョー・テキサコといった。それはまさに、彼が天職を見つけた瞬間だった。彼はそうして、ラサーンのローディー兼パーカッショニストとして、行く先々についていくことになった。
俺は当時、二人の偉大な音楽の予言者から強い影響を受けていた。彼らは、それぞれに音楽を、偽善や憎悪や無知や恐怖に対する武器にしようとしていた。一人は、ラサーン・ローランド・カーク、もう一人が、ジミ・ヘンドリクスだった。彼らは、出会った瞬間から、意気投合し、互いに理解者になった。
ジミは、スランプに陥ると、精一杯がんばろうとしていた。俺は、彼を見て、それがわかった。だが、ラサーンは、それを感じとれた。彼は俺を、わきに連れていき、こう言った。
「ジミに(LSDを)やりすぎるなと言ってくれ。彼はあまりにもいろんなものが見えすぎている。ジミはわかりすぎる。ペースを落とせと彼に言わないと駄目だ」。[次回5/19(月)更新予定]


































