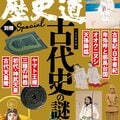保阪:ルーズベルトは1941年12月8日(ワシントン時間7日)、前日の日本による真珠湾攻撃を受けて、議会で有名な「恥辱演説」を行います。これでアメリカの参戦が決まるわけですが、その時、「ドイツは第一次世界大戦で負けたという認識が持てなかった。だからまた戦争をするのだろう」などと新聞記者のインタビューに答えています。「だから今度の戦争は無条件降伏しかない。無条件降伏を日本、イタリア、ドイツに認めさせて、お前たちは負けたんだということを徹底的に教え込む必要がある。途中の和平はない。徹底的に戦う。そして我々が望むデモクラティックな体制を作って、二度と我々に歯向かってこない国にするんだ」というようなことを言った。実際にそうなっていますよね。
池上:第一次世界大戦が人類史上初めての「世界大戦」で、それが前半戦にしか過ぎず、その後半戦があった。つまり、ひと続きの戦争だったと……。
保阪:そもそも、なぜ「世界大戦」と呼ぶのか。どちらも始まりの時点では、誰もあんな大規模な戦争になるとは思わず、みんなすぐに終わるだろうと思っていた。それが関係者の予想を超えて戦線が急拡大して、結果的に世界大戦と呼ばれるようになったわけです。
池上:今日のウクライナ侵攻も、関係国や専門家が「まさか」と思っていた事態です。どこか似ている気がします。
保阪:第一次世界大戦での「まさか」は帝国の崩壊でした。オスマントルコ、ロシア、オーストリア=ハンガリーといった帝国が次々と崩壊した。背景には民族意識の高まりがあり、帝国の網の中にくくられていた国や地域が独立していく。また、戦争にアジアやアフリカの植民地が参戦することで、世界中が何らかの形で関わったわけです。
池上:第一次世界大戦を契機に民族の独立運動や社会主義運動が世界的に広がり、それも第二次世界大戦に引き継がれたといえます。また、第一次世界大戦で「国家総力戦」が初めて行われたとされている。国の軍事力のみならず、経済力まで問われるという点で史上初めて。これも第二次世界大戦に引き継がれたといえます。保阪さんのおっしゃる連結は、こうした意味も含んだ表現ですよね。