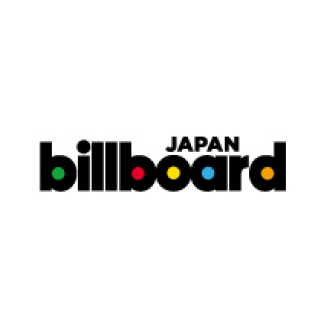コンプトンには、積み重ねた記憶が多すぎる。米西海岸ヒップ・ホップの大物プロデューサー/ラッパーであるドクター・ドレーが、『2001』(1999年)以来実に15年ぶりとなるオリジナル・アルバム『Compton』を、この8月7日に急遽配信リリースした。日本盤CDは、追って9月25日にリリースされる予定となっている。
若い音楽ファンは、ドクター・ドレーという名前に触れて何を思い浮かべるだろうか。もしかすると、あなたが今使用しているBeatsヘッドフォンのプロデューサーとしてかも知れない。カリフォルニア州コンプトン出身のドレーはまず、イージー・Eやアイス・キューブらと共にN.W.A(Niggaz Wit Attitudes)の一員として高い認知を得た。今夏、N.W.Aの名盤デビュー・アルバム『Straight Outta Compton』(1988年)と同名の伝記映画(アイス・キューブが脚本や監修に携わっている)が公開された(日本は公開未定)。ドレーの新作『Compton』は、その映画にインスパイアされた作品である。
そもそもはアメリカン・ドリームを体現する街であったはずのコンプトンが、アメリカで最も犯罪率の高い街のひとつになってしまった――そんなナレーションの「Intro」から始まる『Compton』は、例えば「アメリカ黒人がスターになろうと思ったら、NBA選手かドラッグ・ディーラーになるしかない」(極端な言葉ではあるけれども、あながち的外れでもないところが深刻なのだ)などと囁かれていた1990年代の初頭に、Gファンクという巨大な音楽ビジネスのモデルを打ち立てようとしたドレーの音楽キャリアを強く浮かび上がらせる。
「Genocide」では、コンプトンの若き語り部であるケンドリック・ラマーやUKの女性シンガーであるマーシャ・アンブロージアスを招き、日々身近なところに死の匂いが付き纏うコンプトンを当たり前のように淡々と語る。「All In A Day’s Work」はまるで、働けど働けど我が暮らし楽にならざりけり、といった貧困層の労働歌/ブルースのようだ。西海岸ラップの大御所であるコールド187umが「Loose Cannons」で垣間見せる狂気のラップは圧巻で、そこからアイス・キューブが参加した「Issues」、そして「Deep Water」と続く中盤のシリアスな楽曲連打には思わず息をのむ。
スヌープ・ドッグやイグジビット、エミネムにザ・ゲームといった、ドレーの栄華を語るには欠かせないビッグ・ネームも挙って参加しているものの、改善どころか悪化の一途を辿るコンプトンの実情を前に、アルバムのトーンはひたすらに憤りと、やるせなさと、虚しさが渦巻いていく。長らくリリースが噂されていたアルバム『Detox』はお蔵入りとなり、ドレーは渾身の力で故郷に寄せる思いと向き合い、キャリア最後のアルバムとされる『Compton』を完成させた。天下のドレーが無力感さえ漂わせるような「Darkside/Gone」や、最終トラック「Talking to My Diary」は、涙無しには語れない。しかし、だからこそ、リアリティに徹したドレーには、心からの拍手と賛辞を贈りたいと思うのだ。
[text:小池宏和]
◎リリース情報
『Compton』
2015/08/07 RELEASE(国内盤 9月25日予定)
1,900円
iTunes:https://itunes.apple.com/jp/album/compton/id1024969934