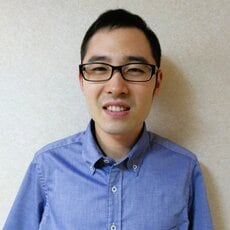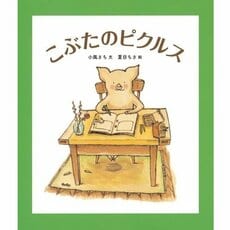1990年代に始まった温暖化防止交渉は、なかなか進まなかった。経済成長には化石燃料によるエネルギーが必要で、CO2の排出を減らすことは経済的にマイナスだと見られていたからだ。
温暖化の脅威が明らかになった2015年、世界は国際ルール「パリ協定」に合意した。産業革命からの気温上昇を2度未満、できれば1.5度に抑えるという内容だが、各国の削減目標が達成されても、気温上昇は3度を超す見込みだ。
IPCCは18年、「温暖化の被害を減らすには、2度ではなく、1.5度未満が重要」と発表。そのためにはCO2排出量を30年に、10年に比べて45%削減。50年には「実質ゼロ」にする必要があるという。「実質ゼロ」とは「カーボンニュートラル」ともいい、化石燃料は原則として使わないが、やむを得ず出したCO2は植林などで吸収するか、地中に埋めて外に出さないということだ。
日本、アメリカ、ヨーロッパなど120カ国以上が50年の実質ゼロを表明。世界最大の排出国である中国も60年実質ゼロを打ち出した。30年の目標についても、日本が46%(13年度比)に変更するなど多くの国が引き上げを表明しており、今秋、イギリスで始まる国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP26)で話し合われる。
温暖化により多くの生命や財産が危険にさらされている。一方で、温暖化防止に役立つ太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギー、蓄電池、電気自動車などの新しい産業は、化石燃料以上の経済効果や雇用を生み出すことがわかってきた。温暖化は「危機」だが「機会」にもなる。
環境などに配慮する企業を重視するESGの投資額は、パリ協定前の14年には約18兆ドルだったが、20年にはほぼ2倍の約35兆ドル(約3800兆円)になった。コロナ禍でもこの流れは変わらない。アメリカやヨーロッパは、コロナ禍からの回復のために、温暖化対策に多額の公的資金を投入する。日本も「グリーン成長戦略」を打ち出した。世界は脱炭素社会に向けてかじを切った。(朝日新聞編集委員・石井徹)
※月刊「ジュニアエラ」 2021年10月号より
朝日新聞出版
![ジュニアエラ 2021年 10 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51TL8MbMxiL._SL500_.jpg)