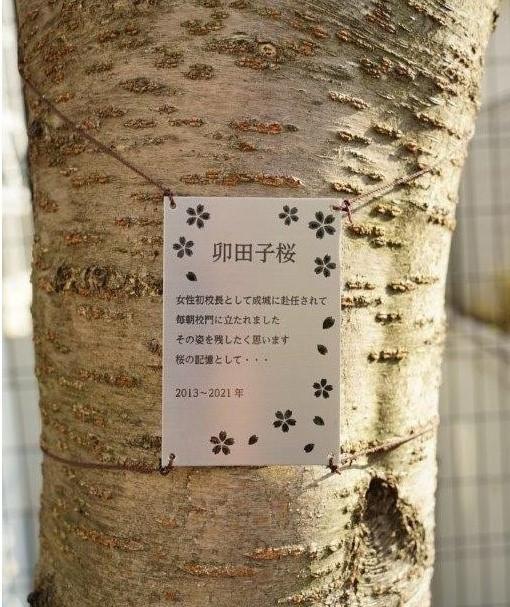しかし赴任前、学校見学に訪れて早々に男子校の洗礼を受けた。校舎を建て替え中だったが、旧校舎は惨憺たる状況。開きっぱなしのロッカーには、きのこが生えた食べ残しのカレーの皿が突っ込まれていた。「男子校はこんなもんですから」。案内してくれた教員は、廊下のごみを拾いながら鷹揚に言った。
「これはまずい、と思いましたね。女性だろうが男性だろうが、学校は気持ち良く過ごす場所でなければいけない。それにこの校舎を見たら、母親は息子に受験をさせたいとは思わないでしょう」
校舎が変われば生徒の意識も変わる。それは、水元高校でかつて経験していたことだった。
「でも校内を回ってみると、生徒がのびのびとして雰囲気がすごくよかった。男子校の良さも感じましたね」
着任早々の4月8日、校長室を一人の中学生が訪れた。
「栗原先生は小石川から来たんですよね。僕らも外国に連れていってくれますか」
唐突な訴えに面食らいながら話を聞くと、生徒は小石川に繰上げ合格候補者となっていたがわずかな差で入学できず、併願校の成城に入学していた。小石川では全員がオーストラリアやシンガポールで研修旅行を行っている。生徒はそれを知っており、直訴しにやってきたのだった。
「海外研修は準備に1年以上かかり、おいそれとできるものではありません。その生徒には、海外にすぐ行くのは難しいけど、他の方法でやってみると答えました」
グローバル教育は海外に行くことでも、英語をただ話すことでもない。行けないのなら、向こうから呼べばいい。ツテを頼りにカリフォルニア大学デイビス校に、大学生の派遣を依頼。逆転の発想で誕生したのが、その年に成城中高で始めた「エンパワーメント・プログラム」だった。
「職員会議で提案したら、大反対をくらいました。今までグローバル教育をやったことがない学校だったので、時期尚早と言われてしまったのです」
しぶる教員を「生徒が望んでいるので、とりあえずお試しでやらせてほしい」と説得。保護者あての説明会のチラシを作って配布した。「10人くればいいだろうと」と、校長室脇の会議室を用意していたところ、想定をはるかに超える180人の申し込みがあった。
「急遽小講堂を押さえてマイクを手配。教頭先生に司会を頼んで、なんとか説明会の体裁を整えました」
次のページへ