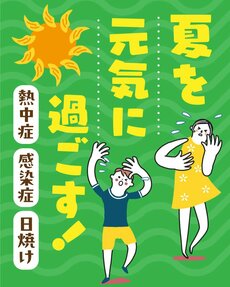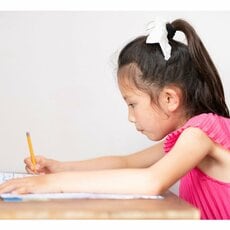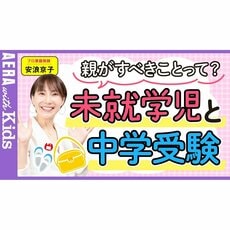人間ってつねに何か考えている生き物で、子どもだってボーッと遊んではいないんですよ。好き勝手にやっている、そんな一見無駄に見える時間のなかに、いつか何かの役に立つ知恵が潜んでいるのです。熱中していれば、その時点でもう「学び」です。人って本来、遊びと学びをスムーズに行き来するのを心地よく感じる動物なのではないかと思いますね。
だから子どものそんな姿をチラッとでも見たら、親は励ましてあげないと。「何してんの?」「おもしろそうだね」とかね。そんな親の一言が子どもの心に響くのです。
そして親は子どもが遊びに熱中するのをただ眺めるのではなく、何が起こるか予測することも大事です。「子どもがこのままやり続けると失敗するだろう」と思っても、それが命に関わることや深刻な事態でなければ見守る勇気も必要でしょう。親は忙しくても、そこは意識的にやってほしいですね。
逆に親は、やってはいけない理由を子どもが理解できるように説明できないと「ダメ!」の一言で片づけてしまいがちですが、これは子どもの意欲を確実に奪います。「こうやってみたら?」と提案できるのが、知恵のある大人ではないでしょうか。
今の親の世代は受験勉強が厳しかった時期に育ったので、子どものころあまり遊んでこなかったかもしれません。だったら、親も童心に返っていっしょに遊びましょう。子どもの気分を理解できますよ。それになにより、子どもは親自身が楽しむ姿を見て、安心して自分の世界に入り込めるのです。
袋に発見を たくさん詰め込んで
僕は「子ども自然教室」を開催し、子どもたちと山に登るなどして遊んでいるのですが、そのとき「これから目的地にいくまでにおもしろいと思ったものは何でも入れていいよ」と一人1枚、ポリ袋を渡しています。目的地でその収穫物を見せてもらうのだけど、そのときの子どもの誇らしげな顔といったら! だから僕も「すごいな、これ」「珍しいね」「よく見つけたね」などと褒めます。こんな一言が子どもを意欲的にし、成長させていけるといいなと思います。もし大人側に知識があれば、子どもの好奇心をもっとくすぐる、知的な言葉もかけられるでしょうね。
次のページへ遊びの経験を豊かにする3つのコツとは?