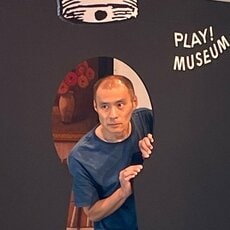子どもの学習がうまく軌道に乗るにはどうしたらよいのでしょう。「このドリルをやらなければ」「机の位置はこうした方が集中できるらしい」などといったよその人の情報を見て一喜一憂するよりも「子どもを正しく捉えて学び方や関わり方を考えるほうが、学習がやりやすくなり子どもも伸びる」と教育家で見守る子育て研究所所長の小川大介さんは話します。多くの中学受験生の親子を見てきた小川さんから、子どもの学びのタイプのとらえ方、学習の関わり方についてアドバイスをしてもらいました。「AERA with Kids 2024年春号」(朝日新聞出版)からお届けします。
【図】「学び方の傾向」がわかる!10のチェックリストはこちら学び方の傾向を知れば、親の働きかけも変わる
「学び方の傾向」を探るチェックリスト(※次ページ掲載)は、子どもの学び方の傾向を知るツールです。人が情報を取り入れるとき、「視覚・聴覚・身体感覚」のどの感覚に反応しやすいか、という点に注目し、小川さんが考案したもの。「普段、こんなところまでちゃんと見ていなかった」と感じる項目もあるのでは?
「このチェックリストで、子どもを観察する視点も知ることができるでしょう。子どもの学びスタイルは、三つの感覚のどこからの情報により強く反応するかによって変わってきます。親はわが子のタイプを知り、どんな声かけをすると子どもが気持ちよく動けるのか考え、実践していくことで、それまでのような努力で解決させようという力みがなくなり、穏やかに見守れるようになります」
そして、子どもだけでなく、親自身もこのチェックリストで自分のタイプを確認してみましょう。子どもと親は優位感覚が違うはず。「子どもに自分の考えを押し付けても反発される」のも理解できるのではないでしょうか。
ただ注意したいのは、このチェックシートは、どれか一つの感覚が100%ではないということです。だれでも複数のタイプが混じっています。そのなかで「この感覚が比較的優位みたい」という視点で観察することが大切です。
次のページへチェックリスト